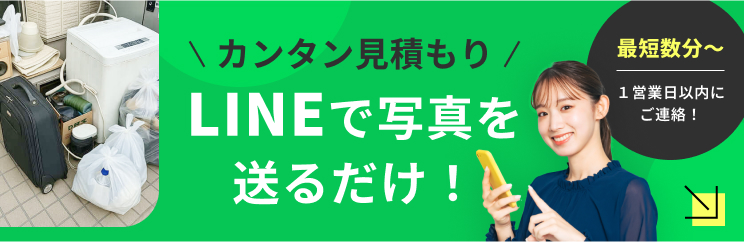雛人形の供養と処分方法・捨て方!取り扱い方・処分時期はいつ?

この記事では、雛人形の供養と処分する方法をご紹介します。
子どもの健康を祈願して飾る雛人形は、供養してから処分する方が良いでしょう。
雛人形を処分するタイミング・時期についても解説していますので、雛人形の処分をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次詳細を見る詳細を閉じる
雛人形の供養と処分方法

まずは、雛人形の供養と処分の方法を紹介します。
処分方法法ごとにメリット、デメリットも解説するので、適切な処分方法を選んでください。
ひな人形の文化的背景と歴史
起源と歴史
ひな人形のルーツは、平安時代(794年〜1185年)の「ひいな遊び」と呼ばれる貴族の子女の人形遊びにさかのぼります。当時は人形を飾るというより、子どもの遊びやお守り的な役割が中心でした。
また、同時期に「流し雛」という習慣が生まれます。これは紙や草で作った人形に自分の穢れを託し、川や海に流すことで厄を払う行事でした。この二つの風習が結びつき、後の「ひな祭り」の基礎となります。
室町時代から江戸時代への発展
室町時代(14世紀〜16世紀)には、貴族の間で人形遊びがさらに広まり、徐々に装飾的な要素が加わります。
江戸時代(17世紀〜19世紀)になると、女の子の健やかな成長を願う「桃の節句(3月3日)」に人形を飾る風習が定着しました。江戸幕府も五節句の一つとして公認し、庶民にも広まっていきます。特に江戸や京都、大阪では地域ごとに特色ある人形が作られるようになりました。
人形の形式と飾り方
当初は内裏雛(男雛・女雛)だけでしたが、江戸時代後期には三人官女、五人囃子、随身や仕丁といった多段飾りが広まります。これにより宮中の婚礼行列を模した豪華なひな壇が完成し、現在の形に近づきました。
人形は子どもの身代わりとして病気や災厄を引き受けると考えられており、「厄除け」と「成長祈願」の意味が込められています。
地域ごとの特色
京都:伝統的な「京雛」は、細部にまでこだわった雅やかな意匠。
関東:江戸時代に発展した「関東雛」は豪華で力強い印象。
東北や北陸:農村部では「立ち雛」や「押し絵雛」といった素朴な様式が伝わる。
現代におけるひな人形
現代でも3月3日のひな祭りに合わせて飾られますが、住宅事情により七段飾りよりもコンパクトな親王飾り(内裏雛のみ)やケース入りの雛人形が人気です。
また、地域によっては今も「流し雛」の行事を行っており、古い形が受け継がれています。ひな人形は単なる装飾品ではなく、子どもの健やかな成長や家族の幸せを願う象徴として大切にされています。
自分で供養して自治体の一般ゴミで処分する
雛人形を自分で供養して、自治体の一般ゴミで処分することができます。
雛人形の供養を自分で行う手順は以下の通りです。
[供養方法]
- 柔らかい布で人形に付着した汚れを取り除く
- 髪の長い人形の髪の毛は束ねる
- 人形を太陽の光に当てて気を満たす
- 通気の良い和紙で人形を包む
- 最後に粗塩を人形にふりかける
- 厄除けをしてくれたお礼を述べる
自宅の庭で雛人形を燃やす「野焼き(焼却施設以外で雛人形を燃やすこと)」は法律や条例で禁止されているため注意してください。
供養が終わったら、自治体の一般ゴミとして出せます。
雛人形の素材によって、ゴミ分別ルールが異なるため、自治体のルールを確認して出すようにしてください。
雛人形は、燃えるゴミや燃えないゴミで出すルールであることが多いですが、7段飾りの雛壇などは「粗大ゴミ」に該当する可能性があります。
【メリット】
- ほぼ無料で処分できる
【デメリット】
- 分別ルールに沿って処分する必要がある
- 供養にやや手間がかかる
神社で供養して処分してもらう
神社では人形供養が行われていることが多いです。
そのため、お住まいの近くの神社に行き、人形供養をしてもらえるか尋ねてみてください。
もし、近くの神社が雛人形の供養を行っていない場合は、一般社団法人日本人形協会にお問い合わせをしてみましょう。
一般社団法人日本人形協会にお問い合わせをすれば、毎年10月頃に東京大神宮で行われる「人形感謝祭り」で供養してくれます。
【メリット】
- 供養と処分をワンストップでできる
- 正式な人形供養なので安心
【デメリット】
- 1体ごとに費用がかかることがある
- 供養をしてくれる神社を自分で探す必要がある
ひな人形を神社に持っていく歴史的・文化的背景
ひな人形は単なる装飾品ではなく、古来より「厄を移す存在」として大切に扱われてきました。そのため処分の際には、神社に納めて供養するという文化が根づいています。
1. 人形と身代わり信仰の起源
奈良時代から平安時代にかけて、人の穢れを人形に移して祓う「形代(ヒトガタ)」の風習が広まりました。『延喜式』(927年)にも記録があり、宮中行事「夏越の祓」では紙や草で作った形代を川に流すことで厄を払っていました。これがやがて「流し雛」となり、賀茂川(京都市)や鳥取県用瀬町などで行われる行事へと発展しました。
2. 江戸時代以降の変化と供養の始まり
江戸時代になると、雛人形は豪華で長く保管されるものとなり、流すよりも「供養する」方向へと変化しました。人形が「子どもの身代わり」と考えられたため、廃棄ではなく神社での祈祷や焼納によって感謝を込めて処分する文化が根づいていきました。
3. 各地の代表的な神社と行事
- 京都・下鴨神社:毎年3月3日に「流し雛神事」を実施。御手洗川に雛人形を流す。
- 鳥取県鳥取市・用瀬町:「流し雛行事」が江戸時代から続き、国の無形民俗文化財に指定。
- 和歌山・淡嶋神社:人形供養の総本山とされ、3月3日には「雛流し神事」を海で行う。
- 東京・浅草神社:毎年10月に「人形感謝祭」を開催し、全国から人形が集まる。
- 東京・本寿院(大田区):年間数万体の人形が持ち込まれ、供養が行われる。
4. 現代における意味
現代では、七段飾りなどを処分できずに困る家庭が増えたことから、全国各地の神社が「人形供養祭」を実施するようになりました。単なる廃棄ではなく、
・子どもの健やかな成長を祈った人形への感謝
・宿った魂を鎮める宗教的な意味
が重視されています。
このように、ひな人形を神社に持っていく処分方法は、古代の形代信仰から流し雛、そして現代の人形供養祭へと連なる、日本独自の文化的背景を持つ習慣といえます。
不用品回収業者の遺品整理サービスで供養・処分する
不用品回収業者が行う遺品整理サービスを利用すれば、雛人形を供養、処分が可能です。
遺品整理サービスは、本来亡くなった方の遺品を整理、片付けるサービスです。
しかし、遺品整理サービスには「供養」のサービスが含まれており、雛人形の処分時にも対応できます。
遺品整理士が在籍している不用品回収業者であれば、丁寧に供養してくれ、その後適切な処分をしてくれるので安心です。
遺品整理サービスだと高くなるので、安く処分したい方は自分で供養して、不用品回収だけを依頼することもできます。
また、雛人形だけでなく、大きな雛壇や桃の造花、ぼんぼりなどの装飾品についてもまとめて回収、処分が可能。
電話1本ですぐに来てくれて、他の不用品も一緒に処分できます。
【メリット】
- 供養・処分をワンストップで依頼できる
- 他の不用品も一緒に処分できる
【デメリット】
- 単品回収だと割高
- 信頼ある不用品回収業者を選ぶ必要がある
雛人形の供養・処分もできる優良不用品回収業者・遺品整理業者ランキングはこちら!
雛人形の供養・処分費用の相場

ここでは雛人形の供養、処分にかかる費用の相場を見ていきましょう。
雛人形の処分費用の平均相場は以下の通りです。
| 処分方法 | 費用相場 |
|---|---|
| 自分で供養・自治体のゴミに出す | ほぼ無料 |
| 神社で供養・処分してもらう | 1,000円〜5,000円/体 5,000円~10,000円/箱 |
| 不用品回収業者の遺品整理サービスを利用する | 3,000円~10,000円 |
処分前に知っておきたい!雛人形の取り扱い方

雛人形の処分方法や処分費用の解説をしてきましたが、そもそも、どのように取り扱うものなのでしょうか?
雛人形を処分する前に「取り扱い方」について理解を深めておきましょう。
雛人形は「女の子の健やかな成長」を願うもの
雛人形は「大切な娘の身代わりとなり厄を引き受けてくるもの」です。
そのため、桃の節句やひな祭りの日に雛人形を飾ると、お嬢様が健康に成長すると言われています。
従来は、雛人形を飾るのは、娘様が嫁ぎに行くまでとされていました。
しかし、現在は結婚にこだわらず、一人前の女性に成長したら処分するものとされています。
生涯を通じて飾り続けることに問題はない
雛人形は娘様が一人前になったら、供養して処分するものですが、生涯を通じて飾り続けることに問題はありません。
大切な娘様の幸せを願って購入した人形のため、飾り続けるご家庭もあります。
自宅に飾る場所がない場合は、実家に飾ってもらってもよいでしょう。
子供や孫に譲り渡すものではない
雛人形を処分するのは「もったいない!」という理由で、子供や孫に譲り渡す方がいますが、絶対に控えてください。
繰り返しになりますが、雛人形は大切な娘様の身代わりとなり厄を引き受けてくれたものです。
雛人形を第三者に譲るという行為は、厄が付いた雛人形を譲るということになります。
そのため、お子様やお孫様の雛人形は別で購入しましょう。
別で購入した雛人形と一緒に飾る分には問題ありません。
雛人形を処分する場合は供養する
雛人形を処分する場合は、厄を引き受けてくれたことに感謝するために人形供養してください。
供養せずに一般ゴミで処分したり、売却したりすると罰が当たるかもしれません。
とてもキレイで高額な雛人形かもしれませんが、供養なしでそのまま処分するのはやめましょう。
雛人形の処分時期・タイミング

ここからは、雛人形を処分する時期、タイミングについて解説します。
実際のところ、雛人形はいつまで飾っても問題ないとされています。
しかし、厄除けの意味合いのある雛人形は譲渡したり、売却したりするのはおすすめできないため、人生の節目で処分する人が多いです。
子どもが成人したとき
子どもが成人したときを節目として、雛人形を処分するのもありです。
現在は、18歳が成人年齢とされていますので、高校卒業を機に処分するのもいいでしょう。
また、成人式を終えたタイミングで「大人になった」という視点で、雛人形を処分する方も多いようです。
子どもが実家を離れるとき
大学に進学した、就職したなど、子どもが実家を離れ、一人暮らしを始めるタイミングで雛人形を処分する方もいらっしゃいます。
雛人形に限らず、実家を離れる=独立することですから、実家で使っていた自分の部屋の片付けをすることも多いです。
「巣立つ」という意味合いで、これまで自分が使っていたものや雛人形などの幼少期からの縁起物などをまとめて処分するのもおすすめです。
まとまった量の不用品を処分するのであれば、不用品回収業者を利用するのが良いでしょう。
パックプランなら、大量の不用品回収にお得に対応しています。
相場より安く対応するおすすめ不用品回収業者ランキングはこちら!
子どもが大人になり結婚するとき
結婚を機に、雛人形の処分を検討する方も多いようです。
結婚=大人になるという意味合いでとらえると、子どもの健康を祈願して飾る雛人形は、処分するタイミングという解釈ができます。
結婚後、出産して自分の雛人形を譲りたいと考える方もいらっしゃいますが、基本的に雛人形を譲ることはNGです。
どうしても雛人形を譲るのであれば、神社などで厄除けをしてもらい、厄を払ってから譲渡する必要があります。
雛人形の供養・処分なら「粗大ゴミ回収隊」へ!

https://sodaigomi-kaishutai.com/
雛人形の供養、処分をするなら「粗大ゴミ回収隊」がおすすめです。
粗大ゴミ回収隊は、遺品整理サービスにも対応しており、お世話になった雛人形を丁寧に供養して処分してくれます。
供養の仕方や雛人形などの縁起物の取り扱いの知識も豊富です。
また、雛人形セットの雛壇、装飾品などもまとめて回収。
業界最安値9,800円からのパックプランなら雛人形以外の不用品回収もまとめて対応できます。
雛人形の供養、処分をお考えの方は、ぜひ「粗大ゴミ回収隊」にご相談ください。
困ったときは無料相談がおすすめ
記事を読んでいて「結局どうしたらいいかわからない」「すぐになんとかしたい」「直接専門家に相談してみたい」という方も多いはず。そんなときは無料相談窓口を利用してみましょう!専門のオペレーターが対応いたします。
 に
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531 お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
に
 に
にまずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

雛人形の供養や処分についてのよくある質問
Q 雛人形の処分前に供養は絶対にしないといけないのでしょうか。
A.雛人形を供養せずに処分したとしても、何かあるわけではありません。
しかし雛人形は、子どもの健康を祈願する「厄除け」の役割があります。
厄を吸収してくれた雛人形には、感謝の気持ちで供養してから処分した方が良いでしょう。
また雛人形は、人の形をしていますので、抵抗がある方も多いです。
神社や遺品整理サービスで供養することもできますが、自分でお清めをして供養する方法もあります。
長年厄から守ってくれた雛人形に感謝して労ってあげましょう。Q 雛人形の供養は、不用品回収業者でもできるのですか?
A.不用品回収業者のなかには「遺品整理」に対応している業者があります。
雛人形の供養は遺品整理とは異なりますが、遺品整理サービスの一環で「供養」にも対応しているため、不用品回収業者でも対応は可能です。
粗大ゴミ回収隊でも遺品整理に対応しています。
雛人形の供養から処分まで丁寧に進めてまいりますので、ぜひご相談ください。Q 雛人形を処分するタイミングはいつが良いでしょうか?
A.雛人形は子どもの「厄除け」の意味合いがあるため「大人になった」タイミングで処分する方が多いです。
・子どもが成人したとき
・子どもが実家を離れるとき
・子どもが大人になり結婚するとき
しかし、雛人形は処分しなければならないという決まりはありません。
ずっと飾っても問題ないものです。
ただし、自分の子どもができた際に、譲渡することは原則NGです。
どうしても譲りたいのであれば神社などで「厄払い」をしてもらってください。