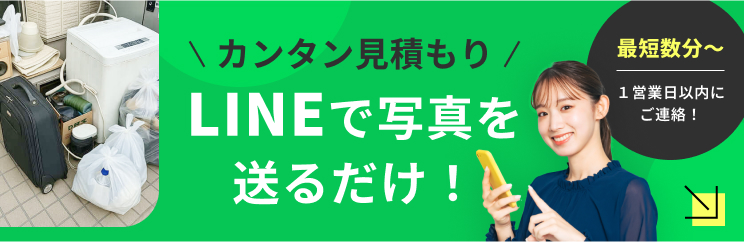残土の処分方法!費用相場や個人での持ち込み可能な処分場も紹介

この記事では、残土の処分について幅広くまとめています。主に建築現場で発生する残土は、場合によっては膨大な量のため処分方法に悩まされますが、実はさまざまな方法で処理が可能です。
記事を読むことで、残土を適切に処分する方法が分かります。処分時の注意点やかかる費用の相場、安く抑えるコツや持ち込みできる処分場も紹介するため、残土をどう捨てるべきか悩んでいる方は参考にしてください。
家庭菜園などで出た残った土の処分方法を確認したい方はこちら!
目次詳細を見る詳細を閉じる
残土とは建設現場で発生した土のこと

残土とは土のことですが、建築現場で発生した土が主に該当します。たとえば、建築物の建設・解体や道路工事などの現場では、地面の掘削や埋め戻し等によって余分な土が発生します。
これらの土は使い道がなく処分されるか、何らかの形で再利用するなど、残土として適切な処分が求められるのです。
残土は「建設発生土」の一般的な呼び方
残土は前述の通り建築現場で発生した土が主で「建設発生土」の一般的な呼び方として浸透しています。自宅にて家庭菜園・ガーデニング等を行なった場合も土は余りますが、これらは残土とは区別されるケースが多いです。
残土は産業廃棄物ではなく処分にはマニフェストも不要
残土は原則として、産業廃棄物には該当しないです。処分にあたってのマニフェストなども不要で、土の適切な処分方法に則って対処ができれば問題はありません。
産業廃棄物は以下の定義で決められており、計20種類が該当します。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
引用元:東京環境局
建築現場で発生する土のため、木・金属くず、コンクリート等が含まれている残土は産業廃棄物に該当するケースがあり注意が必要です。産業廃棄物の混入有無については慎重に確認した上で、適切な処分が求められます。
産業廃棄物20種類
| 区分 | 産業廃棄物の種類 |
|---|---|
| あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス・コンクリート・陶磁器くず・鉱さいがれき類・ばいじん |
| 排出する業種等が限定されるもの | 紙くず・木くず・繊維くず・動物系固形不要物・動植物性残さ・動物のふん尿・動物の死体 |
残土は指定処分が原則
残土自体は産業廃棄物に該当しませんが、処分する際は原則として搬出先を指定しなければなりません。残土が不法投棄されるのを防ぐためにも、このような決まりを設ける自治体が多いです。
残土を処分・回収する業者は、どこの処分場に持ち込むのかをあらかじめ明示する必要があります。
残土の種類は「コーン指数」で異なる

残土の種類は、地盤の強度を表す指標のひとつ「コーン指数」によって以下の5つに分類されます。
| 種類 | コーン指数q(kN/㎡) |
|---|---|
| 第1種建設発生土 | – |
| 第2種建設発生土 | 800以上 |
| 第3種建設発生土 | 400以上 |
| 第4種建設発生土 | 200以上 |
| 泥土 | 200未満 |
参考:国土交通省「建設発生土等の工事間利用調整実施マニュアル」
コーン指数の数値が大きいほど地盤が硬い土、小さいほど軟らかい土になります。種類によって処分方法が異なるものもあるため注意してください。
以下でそれぞれの特徴を紹介します。
第1種建設発生土
第1種建設発生土は良質の砂礫や粘土を主成分として含む、分類の中でもとくに高品質な土です。コーン指数は定められておらず、土地の造成や道路用の盛り土、土木構造物に利用されるなど高品質なゆえ利用の幅も広いです。
第2種建設発生土
コーン指数が800kN/㎡以上の第2種建設発生土は、第1種に比べてやや強度は低く構造物には不向きですが、道路用地の盛り土や地盤改良などの利用価値をもつ土です。
主成分は土砂で、一部砂礫や粘土の成分も混ざっています。基盤材や緑地の土として再利用するために、整形処理を行うケースもあります。
第3種建設発生土
コーン指数が400kN/㎡以上の第3種建設発生土は、水分を多く含んだ粘性の高い土です。第1種・ 第2種に比べると直接的な利用用途が限られており、他の材料と混合する、乾燥処理を施すなどして用途を広げます。
緑化基盤や埋め立て用として再利用できるものの、適切な品質管理が求められます。
第4種建設発生土
コーン指数が200kN/㎡以上の第4種建設発生土は、強度が低く軟らかいのが特徴です。多くの土木工事で再利用が難しく、廃棄処分になるケースが多いです。工事で使う場合には安定剤を混ぜて補強するなど、品質管理を徹底した上で慎重に活用されます。
泥土
コーン指数が200kN/㎡未満の土は、水分をとても多く含んで再利用が難しい「泥土」に該当します。湿地整備などの一部の特殊な工事で再利用されるケースもありますが、管理がとても難しいため処分されるのが一般的です。
残土の中でも、再利用ができない泥土については産業廃棄物として処理する必要があるため注意してください。
「建設汚泥」は産業廃棄物として扱う

建築現場から排出される土には、リサイクル可能なものとそうでないものとがあります。このうち水分を多く含む泥土の中で、廃棄物などを含み再利用が難しいものや、標準仕様のダンプに積み上げられずその上を人が歩けないようなものは、汚泥(建設汚泥)として分類しています。
残土はそのままの状態でほかの用途などに再利用が可能ですが、建設汚泥は土の質が悪く再利用することができません。再利用の可不可が、残土と汚泥の大きな違いです。
建設工事によって排出される水分を含んだ泥土の内、以下のような条件に当てはまるものは「建設汚泥」として取り扱われます。
- 標準仕様ダンプトラックに山積できない
- 山積みにした上を人が歩けない状態
- 運搬の繰り返しで泥状になる
- コーン指数がおおむね200kN/㎡以下
- 一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下
水分が多く、かなりドロドロの状態の土のことを指します。こうした建設汚泥は「産業廃棄物」として処分が必要です。
残土を処分する流れ

ここからは、建設現場から出た残土の処理について、大まかな流れを解説します。
- 残土再利用の促進
- 残土処分場へ運搬
- 残土を改良土に処理
ただし、現場の状況や業者により細かい部分は異なります。
1.残土再利用の促進
国や地方自治体が設定したルールでは、そもそも残土が出ないような設計を求められています。土の余剰分が発生してしまった場合も、現場で使い切るように定められているのです。
どうしても現場で使いきれなかった残土については、他の工事での再利用が検討されます。全国に設置されたストックヤードに残土を一時保管し、再利用の目途が立った場合に運び出される仕組みが整っています。
ストックヤードは公共と民間の2種類があり、公共のストックヤードは原則として公共の工事を行う事業者のみ利用可能です。
2.残土処分場へ運搬
現場での使い切りや他の現場での再利用が難しい残土は、残土処分場で処理してもらうことが可能です。残土処分場は主に山間部や沿岸部に設置されています。
持ち込まれた残土は基本的には埋め戻されますが、土を販売しているケースもあります。残土処分場の受入単価はストックヤードとほとんど同じであり、全国平均で約2,000円/㎥です。
残土の種類は第1種~第4種建設土と泥土の5種類です。残土の種類によっては、処分場で受け入れてもらえないこともあります。
また、木の根やガレキなどが混入した土は、残土ではなく廃棄物です。これらの残土は「ガラ混入土」や「ガラ入り残土」などと呼ばれます。
残土は自然物であり、廃棄物とは明確に区別されます。廃棄物として扱われる土を処分する場合は、混入物を取り除いて残土にする方法や、廃棄物専門の業者に処分を依頼する方法がとられます。
3.残土を改良土に処理
回収された残土は埋め戻されるだけでなく、改良土に処理されるケースもあります。特殊な工法で残土を改良土に処理する施設がリサイクルプラントです。
リサイクルプラントの利用頻度はまだ少ないものの、近年は大規模土石流災害をきっかけに残土リサイクルが注目を集めています。企業によっては現場にプラントを設置し、残土を現場でリサイクルしている場合もあります。
リサイクルプラントの受入単価は、ストックヤードや残土処理場に比べ高めです。
残土の処分方法

残土の適切な処分方法をいくつか紹介します。
残土処分場で捨てる
各地域などに設けられている残土処分場などへ持ち込み、処分する方法があります。残土処分場は民間企業やNPO法人などによって運営されている施設です。
山間部などに設けられていることが多く、持ち込まれた残土のほとんどはそのまま埋め立てという形で処理されます。
残土仮置き場に引き取ってもらう
ストックヤードと呼ばれている、残土の仮置き場に引き取ってもらう方法もあります。ストックヤードはへ運び込まれた残土は、一定期間保管されたのちに適切な形で再利用されます。
ストックヤードを利用するには申請書などが必要となる他、地方公共団体や公共団体発注による現場から出た残土でなければならないなどの条件が伴うこともあります。
処分業者に処分を依頼する
残土処理を行う株式会社・有限会社・NPO法人などの業者に処分を依頼することも可能です。残土処分場やストックヤードよりも拠点数が多いため利用しやすくなりますが、その分費用はやや割高な傾向にあります。
第1種建設発生土〜第4種建設発生土のほか、ストックヤードや残土序文場では受け入れ不可となる泥土や廃棄物が混入した土などの処分ができるところもあります。
残土処分費の相場
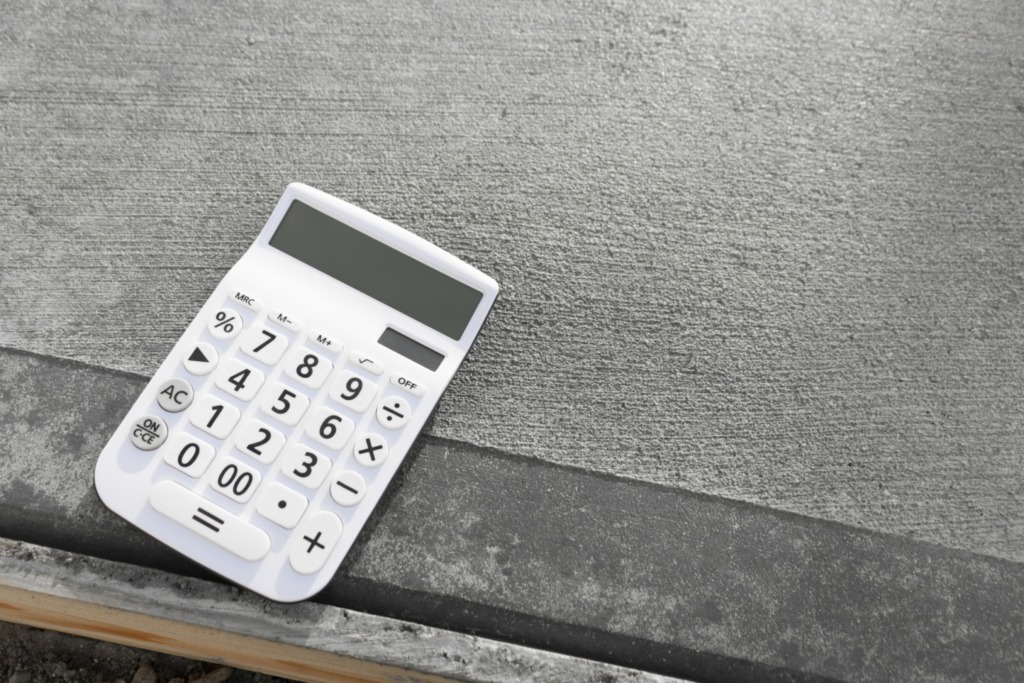
一般的に、残土処分費は運搬に使われる車両のサイズで異なります。残土処分費の相場の目安は次の通りです。
| 車両サイズ | 費用相場(1台あたり) |
|---|---|
| 2t車 | 9,000円 |
| 3t車 | 10,000円 |
| 4t車 | 12,000円 |
| 7t車 | 17,000円 |
木の根やガレキなどが混入した土を受け入れてもらえる場合、上記の金額より費用は高くなります。
残土処分時の注意点

残土を処分する際の注意点にも触れていきましょう。
残土の種類で処分方法に違いがある
残土にはその土質や状態に応じて、いくつかの区分(種類)があります。処分場によっては種類に応じて受け入れ可否が異なります。
残土の種類によって処分方法も変わってくるのです。それぞれの処分場で受け入れ可能な残土や汚泥の区分は以下のとおりです。
- ストックヤード:第3種建設発生土以上の残土・土砂
- リサイクルプラント:第4種建設発生土以上の残土・土砂
- 残土処分場(建設発生土受入場): 産業廃棄物混入土以外(処分場によって異なる場合がある)
- 処分業者:参拝許可を得ている業者であれば産業廃棄物にあたる汚泥や土の処分が可能
建設汚泥は許可のある業者に依頼して処分する
建設汚泥やは土質改良困難が難しく再利用ができないため、ストックヤードや残土処理場などへ持ち込むことができません。また廃棄物まじりの土も同様です。
これらは産業廃棄物に当たるため、廃棄物処理業者などで処分する必要があります。またこうした産業廃棄物に当たる建設汚泥などは、廃棄物運搬の許可を得た車両でなければ運ぶことができません。
処分が必要な際は、産業廃棄物処理業者などに相談するのがよいでしょう。
残土以外の建設副産物は再生資源として処分する
建設現場では残土以外にもさまざまな建設副産物と呼ばれるものが発生します。建設副産物の内、以下のようなものは再生資源として処分が可能です。
- アスファルト隗
- コンクリート塊
- 建設発生木材
- 建設汚泥(土質改良必須)
- 建設混合廃棄物(土質改良必須)
- 金属くず
上記に当てはまらない廃棄物や有害・危険なものは、再生資源として利用できません。
残土処分費を安く抑える方法

残土処分費をできるだけ安くしたい場合は、以下2つの方法を検討しましょう。見積もり金額より費用を抑えられる可能性があります。
個人で残土の捨て場へ持ち込む
残土処分費を構成する要素は主に以下の4つです。
- 重機費
- 運搬費
- 人件費
- 残土処分場の受入費
個人で残土を捨て場へ持ち込めるなら、上記4つのうち重機費・運搬費・人件費を削れることになります。ただし、自分で運搬用の車両を用意した上で、残土の積み込みも自分で行わなければなりません。
費用を抑えられる代わりに、かなりの手間を要する恐れもあります。それでも残土を自分で捨て場へ持ち込みたい場合は、残土処理場や処理業者に相談した上で、指示通りに残土を持ち込みましょう。
値引き交渉をする
残土処分費を安く抑えたい場合は、複数の業者から相見積もりをとるのもおすすめです。3~5社程度から見積もりをとって比較すれば、最も条件の良い業者を選べます。
利用したい業者に他社の見積もりを見せて、値引き交渉を行うのも1つの方法です。他社の見積もり金額と大きな差がない場合は、値引きに応じてくれるケースがあります。
一般的に、残土処理業者は残土を仮置きでためておき、後からまとめて捨てることで経費を抑えています。そのため、見積もり時点での残土処分費は安くなる余地が十分にあるのです。
運搬回数を減らす
残土処分費は基本的に車両1台ごとに料金がカウントされます。車両に積む残土が少ない場合も1台分の料金を請求されるため、割高になってしまうのです。
運搬回数を減らし、1台あたりに目一杯の残土を積むようにすれば、残土処分費を安く抑えられます。車両サイズが大きくなるほど費用は割安になるため、業者を選ぶ際は保有車両のサイズを確認することも重要です。
個人で残土の持ち込みが可能な東京近郊の処分場

処分場の中には、個人で残土の持ち込みが可能な場所もあります。東京近郊で残土の個人持ち込みができる処分場の例をいくつか紹介します。
株式会社サンノウ興業
株式会社サンノウ興業では、第1種〜第4種の残土全般を受け入れ可能です。軽トラックや4tトラック、ダンプカーなどさまざまな車両で搬入可能な点が特徴です。
重量ごとに細かく費用目安も変わるため、費用を安く抑えられる場合があります。
| 施設名 | 株式会社サンノウ興業 |
|---|---|
| 住所 | 〒143-0023 東京都大田区山王4-18-3 |
| 電話番号 | 070-1446-5833 |
| 受付時間 | 7:00 ~ 18:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| 持ち込み費用目安 | 2t:9,000円(税別) 3t:12,000円(税別) 4t:17,000円(税別) 7t:29,000円(税別) 10t:35,000円(税別) |
英建株式会社
英建株式会社では建築現場の残土をはじめ、家庭の庭土も持ち込み可能です。軽トラックから大型ダンプまで搬入に対応、事前予約は不要で急ぎ処分したい場合にも飛び込みで持ち込みができます。
| 施設名 | 英建株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒259-1212 神奈川県平塚市岡崎1295 |
| 電話番号 | 0463-50-3610 |
| 受付時間 | 要相談 |
| 定休日 | 未定 |
| 持ち込み費用目安 | 2t:8,000円(税別) 3t:9,000円(税別) 4t:12,000円(税別) 8t:22,000円(税別) 土嚢袋:1袋200円(税別) 含水費が高い場合は別途割増料金が発生 |
土リサイクルセンター
土リサイクルセンターでは泥土も含めた全種類の残土を受け入れ可能です。(土壌汚染基準を超えた有害土などは不可)費用は土質や量に応じた見積もりで決定、赤土などは一部無料で処分できるサービスもあります。
| 施設名 | 土リサイクルセンター |
|---|---|
| 住所 | 〒333-0833 埼玉県川口市大字西新井宿1374番地 |
| 電話番号 | 048-452-8264 |
| 受付時間 | 要相談 |
| 定休日 | 未定 |
| 持ち込み費用目安 | 要相談 |
有限会社山﨑組
有限会社山崎組では残土をはじめ、庭石などの持ち込み処分にも対応しています。多少の混合物を含む残土も、別途割増料金を支払うことで処分可能です。
土嚢袋については引き取りサービスも実施しており、作業費・運賃等を支払うことで労力をかけずに処分できる点も特徴です。
| 施設名 | 有限会社山﨑組 |
|---|---|
| 住所 | 〒270-1431 千葉県白井市根205 |
| 電話番号 | 047-492-2198 |
| 受付時間 | 8:00~17:00 |
| 定休日 | 日曜、祝日 |
| 持ち込み費用目安 | 土嚢袋:1袋200円~ きれいな土1㎥:6,000円~ 砂利・草混じりの土1㎥:7,000円~ |
個人での残土処分は粗大ゴミ回収隊におまかせ!
個人での残土処分にお困りの方は「粗大ゴミ回収隊」におまかせください。大量にある残土も難なく処分可能、経験豊富なスタッフが迅速に現場に向かって回収します。
回収用トラックのサイズに応じたさまざまなパックプランを、予算や要望に合わせて柔軟に選択できます。残土はもちろん、その他処分困難なゴミや大型ゴミもまとめて片付けられるのが特徴です。
見積もりや出張にかかる費用は無料のため、まずはお気軽にお問い合わせをお待ちしています。
困ったときは無料相談がおすすめ
記事を読んでいて「結局どうしたらいいかわからない」「すぐになんとかしたい」「直接専門家に相談してみたい」という方も多いはず。そんなときは無料相談窓口を利用してみましょう!専門のオペレーターが対応いたします。
 に
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531 お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
に
 に
にまずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

残土の処分に関するよくある質問
Q 残土とはどういう意味ですか?
A.残土とは建築工事や土木工事で建設副産物として発生する土のことをいいます。
正式名称は「建設発生土(けんせつはっせいど)」。そのまま、もしくは土質改良によって再利用が可能です。Q 残土は産業廃棄物ですか?
A.残土は再生資源として利用できるものであり、産業廃棄物に当たりません。
ただし廃棄物が混入している場合や、著しく水分を含んだ「汚泥」に当たるものは産業廃棄物として処理・処分が必要となります。Q 残土と土砂は違うものですか?
A.土砂は地表や地盤などを掘削した際に採取された土や砂など石礫や砂利なども含まれた発生物のことをいいます。
たいして残土は建設工事などで発生する土砂全般を示す言葉です。<br>
いずれも「土砂」に変わりはありませんが、残土は「建設発生土(けんせつはっせいど)」の総称となるため意味合いが多少異なります。Q 残土を処分場に持ち込んで処分する場合、運搬は自身で行う必要がありますか?
A.残土を処分場に持ち込んで処分する場合は、基本的に運搬は自身で行わなければなりません。
そのため、残土の量が多い場合には運搬用のトラック等が必要なのはもちろん、車両に土を積載するのにも手間がかかります。<br>
運搬が困難な場合には、現場まで駆けつけてもらえる回収業者の利用をおすすめします。Q 残土の処分費用に補助金などは使えますか?
A.残土の処分にかかる費用で補助金を利用できるかどうかは、所属する自治体によっても異なります。
自治体によっては家屋の解体等にともない生じた、残土をはじめとする廃棄物の処分に補助金が利用できる地域もあります。<br>
条件や金額等の詳細は、所属する自治体の公式サイトや問い合わせで確認してください。