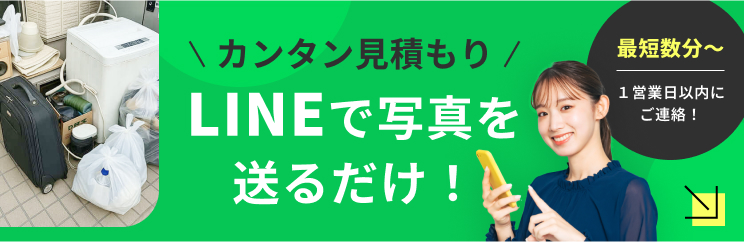ゴミ屋敷の状況をレベル別にご紹介!部屋の片付け方まで徹底解説

2026年8月現在、「汚部屋」と「ゴミ屋敷」には公的に明確な定義はありません。
そのため、
「自分の部屋はゴミ屋敷に当たるのだろうか?」
「汚部屋とゴミ屋敷、サイトによって基準がバラバラで分かりにくい…」
と感じる方も少なくありません。
そこで粗大ゴミ回収隊では、独自に「ゴミ屋敷」と「汚部屋」の基準を表で整理し、その違いを明確にしました。
この基準に沿って現状を判断することで、より適切な改善方法を選ぶことができます。
本記事では、この表に従って、「ゴミ屋敷」に該当する状態について、詳しく解説します。
目次詳細を見る詳細を閉じる
- 1 「ゴミ屋敷」と「汚部屋」の違いの定義
- 2 ゴミ屋敷のレベル(6~10)別状況
- 3 ゴミ屋敷レベルごとの解決方法
- 3.1 レベル6(床が見えなくなる)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
- 3.2 レベル6(床が見えなくなる)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
- 3.3 レベル7(ゴミが膝〜腰の高さ)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
- 3.4 レベル7(ゴミが膝〜腰の高さ)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
- 3.5 レベル8(胸の高さまでゴミが積もる)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
- 3.6 レベル8(胸の高さまでゴミが積もる)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
- 3.7 レベル9(天井近くまでゴミが積み上がる)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
- 3.8 レベル9(天井近くまでゴミが積み上がる)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
- 3.9 レベル10(完全なゴミ屋敷)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
- 3.10 レベル10(完全なゴミ屋敷)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
- 4 その他のケースに当てはまる方へ
- 5 【レベル別】ゴミ屋敷の片付けの費用と時間の目安
- 6 ゴミ屋敷片付けの料金で注意すべき「落とし穴」
- 7 信頼できる業者を見極めるための質問リスト
- 8 ゴミ屋敷の片付けに悩んだら「粗大ゴミ回収隊」
「ゴミ屋敷」と「汚部屋」の違いの定義
「ゴミ屋敷」と「汚部屋」は、一言で言い表すと「生活できないくらい汚い居住状態」「まあまあーかなり汚い居住状態」のように言い換えられ、「重度の汚部屋」と「軽度のゴミ屋敷」の境界線が曖昧になりがちです。
ゴミ屋敷のレベルを把握するには、まずは「ゴミ屋敷」と「汚部屋」の違いを明確にする必要があります。
ここでは、以下のようにゴミ屋敷と汚部屋を定義づけています。
| 項目 | |
|---|---|
| ゴミの量 | 床や通路が見えないほど堆積 |
| 生活機能 | 成立しない(寝食不可) |
| 影響範囲 | 社会問題化・行政対応 |
| 周辺環境 | 悪臭・害虫・火災で近隣被害 |
| 身体面 | 感染症・呼吸器疾患・転倒リスク |
| 精神面 | 孤立・鬱・強いストレス |
| 解決意欲 | 意欲喪失、外部支援必須 |
| 居住環境 | 戸建て・賃貸問わない |
| 感情 | 「片付けたいけど手がつけられない」 「もうどうしたらいいか分からない」 |
| 社会的イメージ | 行政介入・ニュース報道される |
| 項目 | |
|---|---|
| ゴミの量 | 散乱はあるが一部は見える |
| 生活機能 | 成立はするが不衛生 |
| 影響範囲 | 個人の生活内 |
| 周辺環境 | 室内にとどまり、外部影響は少ない |
| 身体面 | アレルギー・睡眠の質低下 |
| 精神面 | 焦燥感・自己嫌悪・改善余地あり |
| 解決意欲 | 意欲は残るが続かず、支援を求めやすい |
| 居住環境 | 戸建て・賃貸問わない |
| 感情 | 「片付けたいけど手がつけられない」 「もうどうしたらいいか分からない」 |
| 社会的イメージ | ネットスラング・ライフスタイルの延長 |
この記事では、上記の基準を基に、さらに分かりやすく伝えるためにゴミ屋敷と汚部屋を10段階に分けて情報をおまとめしています。
- レベル1(汚部屋):小さな散らかり
- レベル2(汚部屋):物や衣類が床に広がる
- レベル3(汚部屋):不衛生な部分が出始める
- レベル4(汚部屋):生活空間の狭まり
- レベル5(汚部屋):悪臭と害虫の発生
- レベル6(ゴミ屋敷):床が見えなくなる
- レベル7(ゴミ屋敷):ゴミが膝〜腰の高さに
- レベル8(ゴミ屋敷):胸の高さまでゴミが積もる
- レベル9(ゴミ屋敷):天井近くまでゴミが積み上がる
- レベル10(ゴミ屋敷):完全なゴミ屋敷
ゴミ屋敷のレベル(6~10)別状況

汚い部屋の状態を10段階に分け、そのうちゴミ屋敷と呼ばれるレベルは5段階(レベル6~10)に分けられます。
それぞれのレベルが、どのような状況であるかを具体的に説明していきます。
レベル6(ゴミ屋敷):床が見えなくなる
当事者の状況:
足元がゴミで埋まり、物を踏まないと移動できません。掃除のしづらさから「どこから手をつけていいのか分からない」と感じ、片付けを先延ばしにしがちです。自力での片付けはほぼ不可能に近づき、精神的にも負担が大きくなります。
参考文献|荒廃した住居の住人に対する精神保健福祉的介入のあり方 東京都立中部総合精神保健福祉センター副所長(公財)東京都医学総合研究所客員研究員 菅原 誠
周囲の視点:
外からは気づきにくい段階ですが、害虫やカビの発生により、家族や同居人が不快感を覚えるようになります。体調不良(咳やアレルギー反応)を訴える人も出てきます。
レベル7(ゴミ屋敷):ゴミが膝〜腰の高さに
当事者の状況:
家具や家電がゴミに埋もれて使えず、ベッドではなく床の上のゴミの上で寝てしまうこともあります。強い悪臭に慣れてしまい、異常さに気づけなくなるケースも多く見られます。
周囲の視点:
隣人や訪問者は玄関先から臭いを感じるようになり、指摘や苦情につながります。宅配業者や管理人が部屋に入れず、生活面に支障が出始めます。
レベル8(ゴミ屋敷):胸の高さまでゴミが積もる
当事者の状況:
室内を移動するにはゴミの山をよじ登る必要があり、転倒や怪我のリスクが高まります。水回りは完全に使えず、コンビニや外食で済ませるため、生活費の負担も増加します。
周囲の視点:
悪臭や害虫が廊下や近隣の部屋にまで拡散します。家族からは「一緒に住めない」と距離を置かれることもあり、孤立感が深まります。集合住宅では管理組合から指導や改善要求を受けるケースも少なくありません。
レベル9(ゴミ屋敷):天井近くまでゴミが積み上がる
当事者の状況:
部屋は圧迫感で息苦しく、生活スペースは数十センチ程度に限られます。ストレスやうつ状態を抱えやすく、健康被害(呼吸器疾患や感染症)のリスクも非常に高いです。
周囲の視点:
異臭や害虫被害が近隣全体に広がり、周囲から「危険な住環境」として認識されます。火災のリスクも高まるため、近所の住民は常に不安を抱えながら生活することになります。
レベル10(ゴミ屋敷):完全なゴミ屋敷
当事者の状況:
生活機能は完全に失われ、部屋で寝食すること自体が困難です。行政や専門業者の介入なしには改善できず、社会的孤立が決定的になります。場合によっては生活保護や福祉サービスの利用が必要になることもあります。
周囲の視点:
近隣住民の生活環境が大きく損なわれ、強い苦情や通報につながります。なお、各自治体によっては「ごみ屋敷条例」や「生活環境保全条例」に基づき、改善勧告や立ち入り調査が行われることもあります。
詳しくは、消防庁や各市区町村の公式サイトで公表されている資料をご確認ください。
参考文献|RILG(条例整備動向)
参考文献|「ごみ屋敷」に関する調査報告書(環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課)
このように、ゴミ屋敷のレベルが上がるにつれて「当事者本人の健康・生活の崩壊」と「周囲への迷惑・被害」が同時に進行します。
放置すればするほど改善が困難になり、費用やリスクも増大します。早い段階で専門業者や自治体の相談窓口に助けを求めることが重要です。
ゴミ屋敷レベルごとの解決方法
ここからは解決編です。
本来であれば、日常的に片付ける習慣を持ち、散らかった状態を放置しないことが最も効果的な解決策です。
しかし、ゴミ屋敷レベルに達してしまった時点で、当事者だけの力で環境を大きく改善するのは難しいのが現実です。
「気合を入れて掃除すればなんとかなる」と考える方もいますが、実際にはゴミの量や不衛生さに圧倒され、途中で諦めてしまうケースが多く見られます。
また、害虫・悪臭・近隣への影響などは本人だけでは解決できない問題に発展していることも珍しくありません。
参考文献|自治体による「ごみ屋敷」対策 ー福祉と法務からのアプローチー(公益財団法人 日本都市センター)
そのため、各レベルに応じた解決法を考える際には、
「自力でできること」と「専門業者や行政の介入が必要なこと」を分けて考えることが重要です。
次からは、ゴミ屋敷のレベルごとに、具体的にどのような手段で改善すべきかを解説します。
レベル6(床が見えなくなる)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
目的:
週末1回で「玄関から寝床・トイレまでの生活導線」を復旧させ、平日も維持できる状態に戻す。
状況想定
間取り:1K〜1DKくらい
18〜25㎡程度(約6〜8坪) のワンルーム規模を想定
前日までの準備(30~45分/1人):
- 45Lゴミ袋(燃える・不燃・資源ごみ用 各8~10枚)
- 段ボール箱(小3~4個)…「保留」「割れ物」用
- 厚手ゴム手袋・マスク・アルコールスプレー・雑巾数枚
- マジックペン(袋に「燃える」「資源」などと書く)
- 飲み物・動きやすい服(長袖長ズボン・滑りにくい靴)
- 自治体の収集日・分別ルールを確認
当日の時間割(合計4~6時間/基本1人、可能なら友人1人):
- 09:00-09:20 換気・安全確認
窓を2か所開けて空気を入れ替え、玄関~寝床~トイレのルートを確認。割れ物や刃物を先に「危険物箱」へ。 - 09:20-10:20 導線確保(玄関・廊下)
足元の物を「燃える」「不燃」「資源」「保留」の4種に分け、袋や箱にどんどん投入。細かい分別精度より“動線優先”。 - 10:20-10:30 休憩
- 10:30-11:45 キッチン周り
生ごみ・液体類は最優先で袋詰め(二重にする)。シンクや床は表面だけアルコール拭き。 - 11:45-12:00 小休憩・換気
- 12:00-13:00 寝床スペース復旧
布団カバーを外して洗濯機へ。床を半畳分でも可視化できればゴールとする。 - 13:00-13:30 トイレ清掃
床と便座をアルコール拭き、消臭剤を設置。 - 13:30-14:00 袋の結束・片付け
全袋の口を固く縛り、収集日まで部屋の一角にまとめる。ビフォー/アフター写真を撮って達成感を記録。
所要時間:1人なら4~6時間、友人1人と協力すれば3~4時間。
おすすめ時間帯:午前9時~14時(体力があるうちに一気に)。
業者介入の目安:
ゴミ袋が10袋以上になって玄関を塞ぐ/虫が大量発生している → 軽トラック回収パックなどの部分依頼を検討。回収作業を業者に依頼する。
維持のための平日習慣(各15分):
帰宅後すぐ「捨てる5分 → 片付け5分 → 水回り拭き5分」。このルーティンを続けると再発防止になります。
レベル6(床が見えなくなる)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
目的:
転倒リスクを減らし、生活導線(玄関・寝床・トイレ)を安全に確保する。体力に負担をかけず、家族や行政のサポートを組み合わせて無理なく改善する。
状況想定
間取り:1K〜2K
20〜30㎡程度(約6〜9坪)の高齢者向け賃貸・団地住まいを想定。新聞紙・チラシ・食品容器などが床を覆っているケースが多い。
前日までの準備(家族またはヘルパーが30分):
- 45Lゴミ袋(燃える・不燃・資源ごみ用 各5〜6枚)
- 段ボール箱(2〜3個)…保留品(思い出の品・通院書類など)用
- 滑り止め付き軍手・マスク・消臭スプレー
- 水分補給用の飲み物、休憩用の椅子の確保
- 自治体の収集日と「高齢者支援サービス(ごみ出し支援など)」の確認
当日の流れ(合計3〜4時間/高齢者1人+家族orヘルパー1人):
- 09:00-09:20 換気・安全確認
窓を開け、段差や滑りやすい箇所を確認。転倒防止のため高齢者は袋詰め作業には参加せず、判断役に徹する。 - 09:20-10:10 導線確保(玄関〜廊下)
家族/ヘルパーが袋詰め。新聞・チラシは「資源ごみ袋」、食品容器は「燃えるごみ袋」へ。高齢者は残す物かどうかだけ指示。 - 10:10-10:25 休憩(水分補給・椅子に座る)
- 10:25-11:15 寝床スペース
布団周辺を優先的に片付け。布団カバーは家族が洗濯へ。床が半畳分見えればOK。 - 11:15-11:30 休憩・消臭スプレー散布
- 11:30-12:15 トイレ周辺
通路の物を撤去し、床をアルコールで軽く拭き取る。消臭剤を設置。 - 12:15-12:30 袋まとめ・保留箱の確認
袋の口を縛り、収集日まで玄関近くにまとめる。重量物は家族が持ち出し担当。
所要時間:3〜4時間。本人は判断のみで体力負担は少なめ。
おすすめ時間帯:午前(9〜12時)…体調が安定している時間帯に実施。
業者・行政介入の目安:
- ゴミ袋が8袋以上になり家族だけで処理が難しい
- 害虫・悪臭が強い
- 高齢者が判断すら困難な場合
→ 自治体の高齢者支援窓口や、シルバー人材センター/専門業者に依頼を検討。
維持のための習慣:
・新聞は読んだらすぐ資源ごみ袋へ(袋は常に椅子の横に設置)
・週1回、家族やヘルパーと「10分点検」を実施し、溜まりすぎを防止。
レベル7(ゴミが膝〜腰の高さ)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
目的:
週末2日を使い、①業者に大物・袋半分を一気に搬出、②本人が生活導線と水回りを復旧する。日常生活を再スタートできる環境を整える。
状況想定
間取り:1K〜1DK(20〜28㎡)
床の膝〜腰までペットボトル・衣類・生活ゴミが積もり、家具・家電の半分が使えない状態。
前日までの準備(1時間/本人):
- 45Lゴミ袋(燃える/不燃/資源 各10〜15枚)、段ボール3箱(割れ物・保留用)
- 厚手手袋・マスク・殺虫スプレー・アルコールスプレー
- オンラインで不用品回収業者に見積り依頼(条件:再見積りなし、階段料金込み、保険加入あり)
- 収集日とマンション規約の確認(エレベーター利用や搬出ルール)
当日の流れ(土曜:業者+本人、日曜:本人のみ)
- 土曜09:00-09:30 業者到着、優先搬出する物(生ごみ・濡れ物・大物)を指示
- 土曜09:30-12:00 業者:大型家具・家電搬出/本人:足元の小物分別(袋詰め)
- 土曜12:00-13:00 休憩・進捗確認
- 土曜13:00-15:00 袋詰め残り半分まで/玄関〜廊下の通路確保
- 日曜09:00-11:00 キッチン・水回り清掃(アルコール+簡易殺虫)
- 日曜11:00-12:00 寝床周辺復旧、布団カバー洗濯
- 日曜12:00-13:00 ゴミ袋の結束・写真記録、保留箱の整理
所要時間: 土曜3〜5時間(本人+業者2名)、日曜2〜3時間(本人1人)
おすすめ時間帯: 午前〜昼過ぎ(9時〜14時)
業者介入の目安:
ゴミ袋が15袋以上になる、冷蔵庫や洗濯機が埋もれている、害虫が広範囲で発生 → 部分回収ではなく「軽トラパック」以上を依頼。
維持のための平日習慣:
・帰宅後「1袋分だけゴミをまとめる」
・週末は必ず“水回りの30分清掃”を固定ルールにする。
レベル7(ゴミが膝〜腰の高さ)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
目的:
転倒リスクと衛生悪化を最小化。1日で生活導線を回復させることを第一目標とし、残りは業者・家族・行政と連携して無理なく片付ける。
状況想定
間取り:1K〜2K(20〜30㎡)
新聞・チラシ・衣類・弁当容器などが膝〜腰の高さまで堆積し、トイレ・台所の使用が困難。
前日までの準備(家族または支援者が1時間):
- 45Lゴミ袋(燃える/不燃 各8〜10枚)
- 段ボール2箱(重要書類・思い出品の保留用)
- 殺虫スプレー・消臭剤・アルコールシート
- 椅子(途中で座れるように)、飲み物
- 自治体の高齢者ごみ出し支援制度を確認、またはシルバー人材センターへ事前相談
当日の流れ(4〜5時間/高齢者+家族2名 or 支援者1名+業者1〜2名)
- 09:00-09:20 換気・安全確認
高齢者は無理せず判断役。家族/業者が袋詰め・搬出担当。 - 09:20-11:00 玄関〜廊下・トイレ導線確保
新聞・紙類を資源袋へ、弁当容器やペットボトルは燃える袋へ。床面を可視化。 - 11:00-11:20 休憩・水分補給
- 11:20-12:30 寝床周辺の確保
布団周りを優先的に撤去。布団は家族が干すかクリーニングへ。 - 12:30-13:00 トイレ周辺清掃・消臭
通路を確保し、アルコール拭き+消臭剤設置。 - 13:00-13:30 ゴミ袋結束・玄関近くにまとめる
所要時間: 4〜5時間。高齢者は判断のみで体力負担は少なく、作業は家族/業者中心。
おすすめ時間帯: 午前(9時〜13時)…体調が安定しやすい時間。
業者・行政介入の目安:
・10袋以上になり自宅に置けない
・害虫・悪臭が強い
・家族が遠方で作業を担えない場合
→ 自治体の生活支援課、シルバー人材センター、不用品回収業者に早期相談。
維持のための習慣:
・新聞・チラシは椅子の横に置いた資源袋へ即投入
・週1回、家族か支援者が訪問し「10分点検」を実施。
レベル8(胸の高さまでゴミが積もる)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
目的:
1日で業者主導でゴミを一括撤去し、最低限の生活空間(寝床・水回り)を取り戻す。本人は「残す物の判断」に専念する。
状況想定
間取り:1K〜1DK(20〜28㎡)
胸の高さまでペットボトル・衣類・食品ごみが積もり、ほぼすべての家具・家電が使えない状態。
前日までの準備(1〜2時間/本人):
- 貴重品(通帳・保険証・契約書・現金・データ機器)を袋にまとめて別室または外部に退避
- 45Lゴミ袋(緊急用に数枚)、マスク、軍手、着替え、飲料水を準備
- 不用品回収業者に「現地見積もり」を依頼(条件:再見積もりなし、保険加入、養生対応あり)
- マンション管理会社・近隣へ作業日を事前連絡(騒音・搬出配慮)
当日の流れ(5〜8時間/業者3〜4名+本人1人立会い):
- 09:00-09:20 作業前打ち合わせ:残す物の指示、搬出ルート確認
- 09:20-12:00 業者:ゴミ袋詰め・搬出/本人:必要品かどうかを即判断(迷う物は「保留箱」へ)
- 12:00-12:30 休憩・進捗確認
- 12:30-14:30 業者:残り撤去、床面の可視化→アルコール噴霧
- 14:30-15:30 仮清掃・消臭剤設置、作業完了報告
所要時間: 業者3〜4名で5〜8時間。本人は立会い・判断のみ。
おすすめ時間帯: 午前開始(9時〜15時)で一気に完了。
業者介入の必須条件:
・部屋全体が生活不能
・ゴミ袋が20袋以上見込まれる
→ 専門業者への「一括撤去+消毒」が前提。
維持のための習慣:
・撤去直後に収納家具を配置して再散乱を防ぐ
・平日は「1日5分ルール」(使った物をその日のうちに戻す)を固定化。
レベル8(胸の高さまでゴミが積もる)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
目的:
安全を最優先に、業者と家族・行政の協力で1日〜2日で撤去・消毒を実施。本人の体力負担を最小限にする。
状況想定
間取り:1K〜2K(20〜30㎡)
胸の高さまで新聞・紙類・容器・衣類が積もり、トイレ・台所は完全に使用不能。害虫・悪臭が強い。
前日までの準備(家族や支援者が対応/1時間):
- 貴重品・必要書類を確認・退避(本人は椅子に座り「残す物」を判断)
- マスク・着替え・飲み物を本人用に用意
- 専門業者に現地見積り依頼(条件:消毒・害虫駆除も含める)
- 自治体の高齢者生活支援課へ相談、費用助成や作業立会いを確認
当日の流れ(6〜9時間/業者4〜5名+家族1〜2名):
- 09:00-09:30 打ち合わせ:本人は判断役、作業員は撤去専任
- 09:30-12:00 業者:ゴミ袋詰め・搬出/家族:思い出品・書類を仕分け
- 12:00-12:40 休憩・水分補給
- 12:40-15:00 業者:残り撤去・大型家具搬出
- 15:00-17:00 消毒・簡易害虫処理・脱臭剤設置
所要時間: 業者4〜5名で6〜9時間。本人は判断のみ、体力負担はほぼゼロ。
おすすめ時間帯: 午前開始で日没前に終了(9時〜17時)。
業者・行政介入の必須条件:
・ゴミ袋が20袋以上/害虫・悪臭が顕著
・本人に体力がなく、家族だけでは対処不能
→ 行政支援+専門業者による「一括撤去+消毒+脱臭」が必要。
維持のための習慣:
・週1回、家族や訪問介護員と「生活導線点検」を実施
・新聞やチラシは玄関に設置した資源袋へ即投入
・「物を入れる箱より“捨てる袋”を部屋の目立つ場所に常備」
レベル9(天井近くまでゴミが積み上がる)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
目的:
建物や健康へのリスクを速やかに取り除き、業者主導で2日間工程(撤去→消毒・脱臭)を完了させる。本人は判断と行政・管理会社との調整に専念。
状況想定
間取り:1K〜1DK(20〜28㎡)
ゴミが天井近くまで達し、ドアの開閉や換気が困難。火災・害虫・悪臭リスクが顕著。
前日までの準備(2〜3時間/本人):
- 貴重品・重要書類・データ機器を退避(段ボール1箱にまとめ外部へ)
- 管理会社へ連絡(作業日時・エレベーター使用・騒音配慮)
- 自治体の環境課/福祉課へ相談し、場合によっては職員立ち会いを要請
- 専門業者2〜3社から相見積り(必須条件:一般廃棄物収集運搬の許可証・損害賠償保険・消毒作業込み)
当日の流れ(2日間/業者5〜6名+本人立会い):
- Day1(撤去 7〜9時間)
09:00-09:30 打ち合わせ(残す物・搬出ルート確認)
09:30-12:00 ゴミ袋詰め・大型家電搬出
12:00-13:00 休憩・進捗確認
13:00-17:00 撤去継続、床面可視化→仮養生 - Day2(消毒・脱臭 5〜6時間)
09:00-12:00 床・壁の消毒・害虫駆除
13:00-15:00 オゾン脱臭・換気
15:00-16:00 作業報告・写真確認・精算
所要時間: 延べ2日間、1日あたり5〜9時間
人数: 業者5〜6名+本人1人立会い
おすすめ時間帯: 午前開始(9時〜17時)で日没前に完了
業者介入の必須条件:
・ゴミが天井近くに達している
・建物の構造や近隣に影響(臭気・害虫)あり
→ 一括撤去+消毒・脱臭が必須。
維持策:
・撤去後すぐ収納家具を設置し「物の仮置きスペース」をつくる
・毎月「ゴミ袋1枚分の整理」を習慣化する。
レベル9(天井近くまでゴミが積み上がる)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
目的:
安全確保と周囲への被害防止を最優先に、行政・家族・業者の連携で2〜3日間で撤去・消毒・脱臭を完了。本人は判断のみを行い体力負担を避ける。
状況想定
間取り:1K〜2K(20〜30㎡)
新聞・紙類・食品ごみ・衣類が天井近くまで堆積し、生活機能が完全に失われている。害虫・悪臭が強く、近隣から苦情が発生。
前日までの準備(家族・行政支援者が対応/1〜2時間):
- 本人に残す物を確認し、貴重品・書類を保管
- 自治体の福祉課へ相談(生活支援・清掃補助・職員立会い調整)
- 業者2〜3社で相見積もり(消毒・脱臭まで含める)
- 近隣へ掲示やチラシで作業周知(苦情予防)
当日の流れ(2〜3日間/業者6〜7名+家族1〜2名):
- Day1(撤去 7〜8時間)
09:00-09:30 養生・打ち合わせ
09:30-12:00 袋詰め・搬出(可燃・資源)
12:00-13:00 昼食・休憩
13:00-17:00 残り撤去、大型家具・家電を搬出 - Day2(消毒・害虫駆除 5〜6時間)
09:00-12:00 床・壁・トイレ・キッチンを中心に薬剤散布
13:00-15:00 害虫駆除・除菌・換気 - Day3(必要に応じて脱臭・確認 3〜4時間)
オゾン脱臭・最終確認、家族・行政と立会い
所要時間: 2〜3日、延べ15〜20時間程度
人数: 業者6〜7名+家族・支援者1〜2名
おすすめ時間帯: 9時〜17時(高齢者の体調・近隣配慮)
業者・行政介入の必須条件:
・本人の生活機能がゼロ
・近隣苦情・衛生リスクが顕在化
→ 行政窓口と連携し「業者+福祉課立会い」で解決。
維持策:
・月1回、家族や訪問介護員が定期的に確認
・新聞やチラシは届いた時点で資源袋へ直行
・再発防止のために「物をため込まない仕組み」を家族と一緒に導入。
レベル10(完全なゴミ屋敷)の解決方法【社会人一人暮らし30代女性向け】
目的:
完全に失われた生活機能を回復させるため、業者主導で複数日工程(撤去→消毒→修繕)を行う。本人は資金調整・行政対応・残す物の判断に専念。
状況想定
間取り:1K〜1DK(20〜28㎡)
部屋全体がゴミで埋まり、天井まで到達。水回り・寝床・電気設備も使用不能。悪臭と害虫が広がり、近隣苦情が発生。
前日までの準備(2〜3時間/本人):
- 重要書類・貴重品は事前に退避(外部のトランクルームや実家へ)
- 管理会社・自治体へ「強制撤去対象になる可能性」を相談
- 業者3社以上から相見積もり(条件:一般廃棄物収集運搬許可・損害賠償保険・分割払いや後払い対応)
- 近隣へ掲示やチラシで作業告知、トラブル回避
当日の流れ(3〜5日/業者6〜8名+本人立会い):
- Day1:撤去開始(7〜8時間)
ゴミ袋詰め・大型家電搬出、搬出ルート確保。本人は「残す物判断」のみに専念。 - Day2〜3:残置物撤去(6〜8時間×2日)
全面撤去。冷蔵庫・洗濯機などリサイクル家電も適正処理。 - Day4:消毒・害虫駆除(5〜6時間)
床・壁・水回りを中心に薬剤散布、オゾン脱臭機で空気浄化。 - Day5(必要に応じて):簡易リフォーム
腐食した床材・クロスを補修、住める状態に回復。
所要期間: 3〜5日間(状況により1週間以上)
人数: 業者6〜8名+本人は判断役
おすすめ時間帯: 9時〜17時、複数日に分けて実施
費用の目安: 数十万円規模。後払い・分割払いの可否を必ず確認。
維持策:
・撤去直後に収納家具・分別用ゴミ箱を導入
・月1回は業者の「定期片付けサービス」や清掃代行を利用し、再発防止。
レベル10(完全なゴミ屋敷)の解決方法【一人暮らし60代高齢者向け】
目的:
安全・衛生を最優先に、行政・家族・専門業者が一体となって強制撤去レベルの清掃+生活再建支援を行う。
状況想定
間取り:1K〜2K(20〜30㎡)
部屋全体が天井までゴミで埋まり、ドアや窓が開閉できない。悪臭と害虫が近隣へ拡散、火災・健康被害の危険が高い。
前日までの準備(家族・行政が主体):
- 本人は判断役。家族が重要書類・薬・医療関連品を確保
- 自治体の福祉課・地域包括支援センターに相談し、生活支援や助成制度を確認
- 業者2〜3社へ相見積り(条件:撤去+消毒+リフォーム対応可能)
- 近隣住民・管理組合へ事前周知(掲示・案内)
当日の流れ(3〜7日間/業者6〜10名+家族・行政):
- Day1〜2:徹底撤去(7〜8時間×2日)
業者が袋詰め・大型家具搬出。家族は残す物の確認。自治体職員が立会い。 - Day3〜4:消毒・害虫駆除(5〜6時間×2日)
床・壁・トイレ・キッチン全体に薬剤散布。ゴキブリ・ネズミ駆除。 - Day5:脱臭・換気(4〜5時間)
オゾン脱臭機を稼働し、空気環境を改善。 - Day6〜7(必要に応じて):簡易リフォーム
床の張替え・クロス補修などを実施。
所要期間: 3〜7日(状況により数週間)
人数: 業者6〜10名+家族・行政
おすすめ時間帯: 9時〜17時
費用の目安: 50〜100万円以上も珍しくない。行政支援・分割払い・福祉補助を必ず検討。
維持策:
・定期的に家族や介護スタッフが訪問して生活点検
・自治体の「ごみ出し支援制度」を活用
・日常的に“ため込まない仕組み”を家族と導入する。
参考文献|消防庁(総務省行政評価局)による調査報告書・事例集
その他のケースに当てはまる方へ
本記事では「社会人一人暮らし30代女性」「一人暮らし60代高齢者」という典型的な2つのパターンを例に解説しました。
しかし実際には、以下のようなケースも少なくありません。
- 戸建て住宅にお住まいの方:
部屋数が多く、1部屋だけがゴミ屋敷化する場合もあれば、家全体に広がるケースもあります。
この場合は、作業日数や費用がマンション住まいより大きくなる傾向があるため、事前に現地調査を依頼するのが確実です。 - 家族世帯・二世帯住宅の方:
家族の誰か1人の生活習慣が原因で部屋が荒れてしまう場合もあります。
このケースでは、本人だけでなく家族全員で「片付けルール」を共有し、再発防止策を整えることが大切です。 - 子育て世帯:
子どもの安全確保(転倒・誤飲防止)が最優先となります。
業者依頼時には消毒・除菌まで一括対応できる業者を選ぶと安心です。
この記事の具体例がそのまま当てはまらなくても、「どのレベルなら自力でどこまでできるのか」「どこから専門業者や行政に頼るべきか」という基準をつかむヒントになるはずです。
もしご自身の状況がここにない場合も、信頼できる業者や自治体窓口に早めに相談し、最適な解決策を一緒に探してみてください。
【レベル別】ゴミ屋敷の片付けの費用と時間の目安

ゴミ屋敷の片付け費用は、ゴミの量・室内の衛生状態・搬出条件(階数やエレベーターの有無)によって大きく変わります。
たとえば同じ1Rでも、床が少し見える状態と天井近くまで積み上がっている状態では、必要な作業人数も日数も異なります。
また、害虫・悪臭・リフォームの必要性によっても追加費用が発生する場合があります。
以下は「足の踏み場がない程度の一般的なゴミ屋敷」を想定した費用と作業時間の目安です。
正確な金額は出張見積もりが必須ですので、参考値としてご覧ください。
| 間取り(広さ目安) | 作業時間の目安 | 片付け費用の目安 |
|---|---|---|
| 1R〜1K (18〜25㎡) |
作業員2〜3名で1〜3時間 | 約30,000円〜80,000円 |
| 1DK〜2DK (25〜40㎡) |
作業員3〜4名で3〜5時間 | 約50,000円〜120,000円 |
| 2LDK〜3DK (40〜60㎡) |
作業員4〜6名で5〜8時間 | 約100,000円〜200,000円 |
| 3LDK以上 (60㎡〜) |
作業員5〜8名で1〜2日 | 200,000円〜要見積もり |
※上記は「床が見えない程度に散乱」「軽度の害虫・悪臭あり」「エレベーター使用可」という標準条件を想定しています。
重度(胸〜天井まで堆積、害虫大量発生など)の場合は追加人員や日数が必要となり、費用もさらに高額になる傾向があります。
ゴミ屋敷片付けの料金で注意すべき「落とし穴」
ゴミ屋敷片付けの費用は、「このくらいの金額だろう」と一般的な相場を見てから業者を探す方が多いでしょう。
しかし、その流れが悪質業者に引き寄せられる原因にもなっています。
よくある流れ:
- 相場サイトで不用品回収業者Aの費用を確認する
- 「思ったより高い」と感じる(再検索を行う)
- 格安をうたう不用品回収業者B(悪徳業者)を見つける
- 基本料金は安いが、実際には追加費用が重なり結果的に不用品回収業者Aの提示額より高額に…
- 不用品回収業者にはぼったくり業者が多い!という印象を持つ
このような流れによって、多くの方が悪徳業者の被害(もしくは、心の中で「思ってたより高いけれど…」ともやもやが消えない経験)を体験することになります。
こういった経験を避けるには、不用品回収業界のビジネスモデルに着目すると、納得感を得て、リスク回避能力を高めることができます。
業界全体の「最低コスト」は大きく変わらない
不用品回収やゴミ屋敷片付けのビジネスには、業者側に以下のコストが発生します。
最低限かかるもの
- 作業員の人件費
- トラックなどの車両費(燃料・高速料金含む)
- 処分場への持ち込み料金(廃棄物処理費用)
- 損害賠償保険や許可証維持のコスト
それ以外でかかるもの
- ゴミを適切に処分するための処理ルートの維持費
- 搬出時の養生・安全管理にかかる備品や教育費
- トラックの車両メンテナンスや駐車費用
- 法律に基づいた処分証明や事務手続き
- 事故や破損に備える損害賠償保険の加入費
- 急な依頼に対応できるようにする待機体制の維持費
これらを踏まえると、どの業者も度を越えた「極端に安い価格」で提供することは現実的に難しいといえます。
むしろ異常に安い業者は、追加料金方式や不法投棄などのリスクを抱えている場合があるため注意が必要です。
極端に安い業者のからくり
「相場より極端に安い業者」に出会った場合、その理由は大きく3つに分けられます。安いからといって必ず悪質とは限りませんが、からくりを理解して見極めることが大切です。
① 健全に安くできるケース
- 買取で費用を相殺: 家具や家電に再販価値があれば、その分を差し引いて費用を抑えている。
- 独自のリユース・リサイクルルート: 海外輸出や提携リサイクル業者により処分コストを削減。
- 自治体・法人との連携: モデル事業や大量受注によりスケールメリットを出せる場合もある。
② 戦略的に安く見せるケース
- 引っ越し業者: 引っ越し受注をメイン収益とし、不用品回収は格安で提供。
- ハウスクリーニング業者: 清掃や原状回復を本業とし、不用品処分は付帯サービス。
- 遺品整理業者: 遺品整理・供養を主軸とし、不用品回収部分は薄利。
- 解体業者: 建物解体の受注を狙い、不用品撤去を「入口商品」として安く提供。
③ 悪徳業者のケース
- 追加料金の上乗せ: 基本料金は安く見せ、現場で「階段料金」「人件費」などを次々請求。
- 不法投棄: 正規の処分費を払わず山中や河川に廃棄し、後に依頼者が責任を問われることも。
- 無許可・無保険: 一見安いが、損害賠償保険や収集運搬許可を持たず、事故やトラブル時に補償なし。
ポイント:
安さの理由が「健全」か「戦略的」か「悪徳」かを見極めることが重要です。
必ず見積もりの内訳・追加料金条件・許可や保険の有無を確認しましょう。
料金で必ず確認すべきポイント
- 基本料金に含まれる内容(搬出費・階段作業・人件費・車両費など)
- 追加料金が発生する条件(夜間・急ぎ・2階以上の搬出・分別代行など)
- 見積もり後に料金が変わる可能性があるか(再見積もりの有無)
「基本料金が安い=最終的に安い」とは限らないということを理解しておくことが、悪質業者を避ける第一歩です。
信頼できる業者を見極めるための質問リスト
見積もりや問い合わせの際には、以下の点を確認しておくと安心です。回答が不明確な業者や曖昧に濁す業者は注意が必要です。
| 確認したい質問 | チェックポイント |
|---|---|
| 基本料金に含まれる内容は? | 搬出費・階段作業費・人件費・車両費が含まれているかを確認。 |
| 追加料金が発生する条件は? | 夜間作業・急ぎ対応・2階以上からの搬出・仕分け代行などの条件を明確に。 |
| 見積もり後に再見積もりはある? | 「現地で追加請求しません」と明言できる業者が望ましい。※当日に追加回収物が無い場合 |
| 許可や資格を持っていますか? | 一般廃棄物収集運搬業の許可証、産廃収集運搬許可証を確認。 |
| 保険に加入していますか? | 搬出時に壁や床を傷つけた際に補償できる損害賠償保険の有無を確認。 |
| 処分後の証明はもらえますか? | 処理証明書やマニフェスト伝票を発行できる業者は信頼性が高い。 |
料金の安さだけで判断するのではなく、「料金内訳・追加条件・許可・保険・証明」を確認することで、健全な業者と悪質業者を見極めることができます。
ゴミ屋敷の片付けに悩んだら「粗大ゴミ回収隊」
ここまで、ゴミ屋敷のレベルごとの状況や解決方法、そして業者選びの注意点について解説してきました。
レベル6や7の段階であっても、放置すれば火災リスク・健康被害・近隣トラブルに発展しかねません。大切なのは「早めに正しい方法で行動すること」です。
粗大ゴミ回収隊は、徹底した経費削減で業界水準の中でも安心価格を実現し、さらに許可・保険完備で安心してご依頼いただける片付け専門業者です。
見積もりは完全無料、金額に納得いただけなければキャンセル料も一切不要。初めての方でもリスクなくご相談いただけます。
当記事では、実際に見積もりを依頼する際の質問事項をご用意させていただきました。粗大ゴミ回収隊はこれらの質問に全て真摯に回答させていただきますので、安心してお問い合わせください。
ゴミ屋敷の片付けでお困りの方は、ぜひ一度「粗大ゴミ回収隊」にご相談ください。
無料の出張見積もりはこちらから
困ったときは無料相談がおすすめ
記事を読んでいて「結局どうしたらいいかわからない」「すぐになんとかしたい」「直接専門家に相談してみたい」という方も多いはず。そんなときは無料相談窓口を利用してみましょう!専門のオペレーターが対応いたします。
 に
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531
お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
に
 に
に
まずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

汚部屋・ゴミ屋敷の片付けでよくある質問
- 作業完了後にお支払いが可能
- 一括払い・分割払いから選べる柔軟な決済方法
- 信販会社との契約による安心・透明な仕組み
- 見積書にはクーリングオフの記載もあり、消費者保護が万全
- 部品やタイヤのサイズや数量によって料金が変動する場合がある
- オイルやバッテリーなどの液体を含むものは、回収可否が異なることがある
- 重量物の場合、搬出の際に追加費用が発生することがある
- 退去日が迫っており、早急に回収してほしい
- 搬出経路が狭く、自分では運び出せない
- 解体や分別が必要で作業が大変
- 他の不用品もまとめて回収してほしい
- お問い合わせ: 粗大ゴミ回収隊のサイトよりお問い合わせいただけます。
- 見積もり: 現地にて実際に回収する品物を確認し、見積もりを行います。
- 回収作業: 承認いただいた後に、安全かつ迅速に回収作業を進めます。
- 費用のお支払い: 作業完了後、ご指定いただいた方法でお支払いをお願いいたします。
Q 後払い決済対応は可能ですか?
はい、可能です。後払い決済をご希望の際は、以下の流れに従ってご対応させていただきます。
粗大ゴミ回収隊では、後払い・分割払いが可能です。
「今すぐ片付けたいけれど、手元に現金がない…」そんな場合でもご安心ください。
当社では、信販会社ライフティ株式会社の後払い決済サービス「WEぶんかつ」をご利用いただけます。
サービスの特徴
事前に「後払いを希望」とお伝えいただくだけで、手続きもスムーズに進められます。
回収サービスを安心してご利用いただけるよう、当社がしっかりサポートいたします。
Q ガレージに保管していた古タイヤや車部品の処分も対応していますか?
ガレージに保管していた古タイヤや車部品の処分も対応していますか?
はい、自家用車の不要部品や古タイヤ、工具類も回収可能です。
特にガレージに長年保管していた古タイヤやホイール、バッテリー、車のパーツなどは、処分方法に悩まれる方が多いですが、粗大ゴミ回収隊ではこれらの回収にも対応しています。内容によっては別途料金が発生する場合がございますので、以下のような点を事前にご確認いただくと安心です。
もし処分をご検討中の場合は、回収品の種類や量、保管状況などを詳しくお聞かせいただけますと、より正確なお見積もりが可能です。お手数ではございますが、ぜひ一度粗大ゴミ回収隊の公式サイトからお気軽にお問い合わせください。スムーズな回収のご案内をさせていただきます。
Q 引っ越しに合わせて壊れたベッドフレームだけ処分したいです
壊れたベッドフレームの回収について
はい、壊れたベッドフレームの回収も承っております。分解作業も含めてお任せいただけますので、重くて処分が難しい家具も安心してお任せください。
引っ越しに伴うベッドフレーム処分をご検討の方へ
引っ越しを機に、壊れたベッドフレームだけを処分したいというご相談も多くいただきます。粗大ゴミ回収隊では、以下のようなご事情にもしっかり対応しております。
ベッドフレームはサイズが大きく重量もあるため、処分する際は搬出の安全性や解体の手間が問題になることが多いですが、当社ではスタッフが分解から運び出しまで対応いたします。女性の一人暮らしやご高齢の方など、お一人では作業が難しい場合も安心です。
お見積もりやお問い合わせについて
粗大ゴミ回収隊では、お見積もりは無料で承っております。また、急なご依頼にも柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは、粗大ゴミ回収隊の公式サイトをご覧いただけますと、サービス内容や料金の目安をご確認いただけます。
引っ越しをスムーズに進めるためにも、壊れたベッドフレームの処分でお困りの際は、ぜひご相談くださいませ。
Q エアコンの配管ホースや金具だけの処分もできますか?
エアコン解体後の部品回収について
エアコン取り外し後に残った配管ホースや金具などの部品は、当社が丁寧に回収いたします。小さなパーツでも見逃すことなく、お客様のご要望に応じたサービスを提供しますので、ご安心ください。
よくある質問:配管ホースや金具だけの処分も可能ですか?
はい、可能です。不用品回収の専門業者として、エアコンの配管ホース、金具、ネジなどといった小さな部品まで、しっかり回収・処分いたします。こちらの作業は頻繁にご依頼いただく内容であり、経験豊富なスタッフが対応していますので、安心してお任せください。
不用品回収の流れ
さらに安心の不用品回収サービス
私たちは、お客様の疑問や不安を解消しながら、プロの視点で最適なサービスを提供しています。不用品回収に関する詳細や料金について知りたい方は、ぜひこちらをご覧ください。