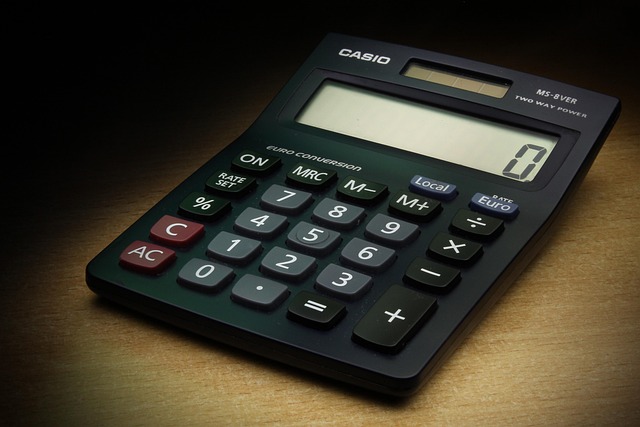空き家の解体費用を誰が払うのか解説!相続の有無や平均金額も紹介

空き家の解体費用について、誰が支払うべきなのかを解説します。
空き家を解体する際は、所有者が誰なのか、相続の有無はどのような状況なのかを確認しなければなりません。
誰が負担するのかは建物の所有状況や相続の進行状況により、大きく変わります。親から受け継いだ家屋や兄弟間での遺産分割、相続権を放棄したケースなど、それぞれの事情に応じて責任者が異なるため、事前に正確な知識を身につけておくことが重要です。
本記事では法的根拠に基づいた状況別の負担者を解説するとともに、取り壊しに必要な費用の相場や軽減方法についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次詳細を見る詳細を閉じる
空き家の解体費用は誰が払うのかケース別に紹介

空き家の解体費用は、基本的に所有者の負担です。しかし、相続した方が複数人いる場合や相続を放棄した場合など、空き家の状況により支払う方が異なります。
誰が払うべきなのかが明確になるので、該当するケースを参考にして空き家の解体費用を払う方を判断しましょう。
相続した空き家の場合
遺産として受け継いだ建物であれば、所有権を取得した承継者が取り壊し費用を支払います。
そのため、空き家を相続する場合は、遺産分割協議の中で解体費用の負担方法についても決定しておくことが重要です。
費用の負担が重くなりがちなので、自治体の助成制度や融資の利用、更地での売却といった手法を選択肢に入れることで、承継者の経済的負担を軽減できます。
相続を放棄した空き家の場合
相続権を放棄した建物の費用支払い義務者は、相続財産清算人と呼ばれる第三者です。
相続財産清算人とは、家庭裁判所によって選任される財産管理の専門家のことで、弁護士や司法書士が任命されることが多くあります。相続人が存在しない状況で遺産を清算し管理する責務を担い、建物の取り壊し費用も含めて相続財産清算人が正式に手続きを進行してくれるでしょう。
そのため、相続権を放棄した方は建物の取り壊し費用を支払う義務はありません。ただし、相続財産清算人が決定されるまでの期間は、建物の管理に関する費用を負担する可能性もあるため、注意が必要です。
また、相続財産清算人が選任されていない状況で取り壊した場合は、依頼した方が費用を支払わなければなりません。
複数の相続人がいる空き家の場合
複数の相続人がいる空き家の場合は、相続人全員で解体費用を分担します。
空き家が共有名義となっており、持分割合が定められている場合には、応じた費用を支払わなければなりません。
ただし、遺産分割協議の際に特定の相続人が費用を負担するよう、合意されている場合には一人が負担するケースもあります。
また、分担する費用を捻出できない方がいる場合は、一部の相続人が立て替えてあとからほかの相続人に請求可能です。
費用負担はトラブルになりやすいことから、空き家を共有名義にて複数人で相続する場合は、持分割合を決めておきましょう。
実家など相続を放棄した空き家の解体の注意点

相続を放棄した空き家の解体に関する注意点として、管理責任や相続財産清算人の選出が挙げられます。
知らないまま空き家を解体するとなると、相続を放棄しているにもかかわらず費用を負担しなければならなくなるので、ここで確認しましょう。
相続放棄後でも一時的に管理責任が残ることがある
空き家の相続を放棄した場合でも、相続財産清算人が決まるまでは管理責任が残ります。ただし、空き家の管理責任のみであることから、基本的に解体に関する費用負担はありません。管理責任が残った場合は、次のような費用がかかります。
- ゴミ屋敷にしないための清掃費用
- 倒壊や人物、動物の侵入を防ぐための修繕費用
ただし、弁護士や司法書士によって見解が異なる場合もあります。基本的には民法に基づいた意見となりますが、結論は裁判の結果で判断されるため、一概にほかの費用を負担しなくてよいわけではありません。
そのため、相続を放棄しても空き家の管理や解体に関する費用負担を強いられることもあるでしょう。
全員が放棄したときは「相続財産清算人」を選任して対応する
相続人全員が相続放棄した場合には、相続財産清算人の選出が必要です。基本的には利害関係人と呼ばれる債権者や特別縁故者などが、申し立てをおこないます。
そのため、基本的には相続を放棄した方が選出する必要はありません。ただし、相続財産清算人が決定しないまま放置された空き家にも管理責任が生じ、倒壊した場合には損害賠償を請求されることもあります。
義務ではないからといって相続財産清算人を選出しないまま放置すると、想定外の費用が発生するリスクがあるので、選出する方がいない場合には相続を放棄した方が家庭裁判所に申し立てをおこないましょう。
兄弟姉妹で相続した空き家の解体費用分担のポイント

空き家を兄弟や姉妹で相続した場合は、解体にかかる費用を分担します。しかし、分担方法がわからずに押し付け合ってしまうと関係が悪くなってしまうので、正しく分担できるポイントを把握しましょう。
適切な分担できれば、家族間のトラブルを避けられます。
持分割合に応じた費用負担
空き家の解体費用を兄弟や姉妹で分担する際は、持分割合に応じた費用負担がおすすめです。
持分割合とは、不動産のような遺産を複数の相続人で共有して相続する場合に、各相続人が持つ所有権の割合のことを指します。
空き家の場合も同じく持分割合に応じた所有権を分配でき、解体費用の分担も算出可能です。
兄弟や姉妹のみで相続した場合の持分割合は人数で均等に割り振ります。2人なら折半し、3人なら1/3ずつ負担する形です。
それぞれの年収や財産にかかわらず負担額を均等に割り振れるので、トラブルが起こりにくい方法といえるでしょう。
家族間トラブルを避けるポイント
家族間のトラブルを避けるためには、法律に基づいた持分割合での費用負担がおすすめですが、話し合うことが最も重要といえます。
たとえば、一企業の社長である兄と専業主婦の妹で費用負担を分担する場合、持分割合は1/2ずつですが収入に大きな差があるため、そのまま持分割合で費用負担を強いられると、専業主婦である妹のほうが厳しい状況に陥るでしょう。
不満が募ると関わりを絶つようなトラブルにも発展しかねないことから、互いを気遣って話し合ったうえで決めることが大切です。
空き家の解体にかかる費用相場

空き家の解体費用を誰が支払うのか明確にしたあとは、実際にかかる費用の相場も確認しましょう。空き家の解体にかかる費用相場は、次のとおりです。
| 建築様式 | 解体費用相場(1坪) |
|---|---|
| 木造 | 3~6万円 |
| 鉄骨造 | 4~7万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 6~9万円 |
上記の相場に基づいて算出すると、木造の一般住宅(戸建て)で30坪と仮定した場合の解体費用は、90~180万円といえるでしょう。
ただし、立地条件や付帯工事により金額は大きく変わるので、正確な料金を知りたいときは業者に見積もりを依頼してください。
空き家の解体には、単純な解体工事費用のみではなく、中にあるゴミや家具の処分や外構の撤去費などもかかります。
空き家の解体費用が払えないときの対処法

空き家を相続したものの、解体費用が払えずに放置してしまうケースもあります。空き家の解体費用が捻出できないときは、補助金制度の利用や解体ローンを組むことがおすすめです。
ここで解説する空き家の解体費用が払えないときの対処法を参考にすれば、相続した空き家の悩みを解決できるでしょう。
補助金制度利用する
解体費用が払えず、放置されている空き家は多くあります。しかし、放置されている空き家には、犯罪に利用されるリスクや倒壊するリスクがあるため、解体を望む声が多くあるのも事実です。
各自治体では、空き家の解体に対する補助金制度を設けています。地域により金額は異なりますが、解体費用の1/2や1/3を補助金で賄える場合が多くあるので、空き家の住所がある自治体に確認してみてください。
上限金額は20万円の地域もあれば、50万円までとする地域もあります。補助金制度を利用すれば、少ない費用負担で空き家を解体できるので、費用が捻出できないときに活用してみましょう。
空き家の解体ローンを組む
空き家の解体費用は、ローンを組んで支払えるので、一括で支払えないときに活用してみてください。
主に地方銀行や信用金庫で申し込める場合が多くあります。とくに空き家の解体に注力している地域では、取り扱う銀行が多くあるので、金利の低さや審査の通りやすさから選択可能です。
また、空き家の解体ローンは担保や保証人が不要なケースが多く、利用しやすいローンである点も対処法としておすすめといえるでしょう。
空き家ごと不動産を売却する
空き家を解体せずに、土地ごと売却する方法も対処法として効果的です。
建物を残して売ることで解体費用がかからないことに加え、売却益を得ることもできます。しかし、建物の老朽化や状況により買い手がつかないこともあるため、手放すまで一定の期間が必要な点には注意が必要です。
仮に売れるか不安な場合には、更地にしてから土地を売却し、解体費用を回収する方法も検討してみましょう。一時的に解体費用はかかるものの、土地が売れればあとから回収できる可能性が高くなります。
空き家を解体せずに放置するリスク

空き家を解体せずに放置すると、倒壊や不法侵入などのトラブルにつながるリスクがあります。
解体費用がかからないメリットよりも、放置するデメリットのほうが多くあるので、リスクを確認したうえで空き家の処分を検討してみてください。
倒壊や特定空き家の指定などの金銭的リスク
空き家を放置すると倒壊や特定空き家の指定などによる、金銭的なリスクが挙げられます。
仮に倒壊して第三者や公共物へ損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うことになるでしょう。
損害賠償額は非常に高額で、人身事故となった場合には数億円にもなります。
また、放置し続けて特定空き家の指定を受けてしまうと、住宅用地の特例措置の対象から外されてしまい、固定資産税の優遇措置が適用されません。
さらに、自治体から改善の勧告を受け、応じなかった場合には最大50万円以下の過料が科せられることもあります。
犯罪の助長や不法侵入などの治安悪化リスク
空き家を放置した際のリスクは金銭的なもののみではなく、地域の治安悪化リスクも含まれています。
たとえば、放置された空き家は犯罪者の隠れ家として利用されやすいほか、犯罪に使用された凶器を隠されてしまうこともあるでしょう。また、不法侵入されて中を荒らされるリスクもあります。
空き家がある地域全体に危険をもたらしてしまう可能性があるので、空き家は放置せずに適切な方法で処分または再利用を検討しましょう。
特定空き家指定時の固定資産税の増加リスク
行政代執行による強制解体での費用請求リスク
まとめ:空き家の解体費用を最小限に抑えるには
空き家の解体費用は、少なく見積もっても100万円単位になります。そのため、最小限に抑えるための対処法や業者選びが重要です。
「粗大ゴミ回収隊」なら、解体工事と家財の処分を一括で依頼できます。ゴミの処分と解体工事を別々の業者に依頼する手間を省けるほか、一括で依頼すれば割引も受けられるので、お得に依頼可能です。
空き家の解体費用を最小限に抑えたい方は、ぜひ検討してみてください。
>>>粗大ゴミ回収隊への無料見積もりはこちら!
 に
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531
お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
に
まずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

 に
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531
お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
に
 に
に
まずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

空き家の解体費用に関するよくある質問
-
Q 空き家の解体費用は誰が払うのですか?
A.原則として、空き家の所有者が負担します。
相続した場合は相続人、共有名義なら持分割合に応じた負担が基本です。
相続放棄をしていなければ、所有権のある人に支払い義務が発生します。 -
Q 相続を放棄すれば、空き家の解体費用を払わなくてよくなりますか?
A.相続放棄をしても、一定期間は管理責任が残る場合があります。
特に危険な状態の建物を放置して倒壊や事故が起きた場合には、費用を請求される可能性もあります。
完全に関係を断つには、家庭裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらう必要があります。 -
Q 兄弟姉妹で相続した場合、解体費用はどう分担すればよいですか?
A.基本的には登記上の持分割合に応じて費用を負担します。
ただし、実際の支払いは話し合いで柔軟に決めることも可能です。
トラブル防止のためには、負担割合や支払い時期を文書で取り決めておくのがおすすめです。 -
Q 空き家の解体費用が払えないときはどうすればいいですか?
A.自治体の補助金制度を活用したり、解体ローンを利用したりする方法があります。
また、老朽化が進んだ家の場合は「空き家ごと売却」して費用をまかなうことも可能です。
早めに専門業者や自治体に相談することで、負担を減らせるケースもあります。 -
Q 空き家を放置すると、どんなリスクがありますか?
A.倒壊や不法侵入などのほか、特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になるおそれがあります。
最悪の場合、行政代執行で強制的に解体され、費用を請求されることもあります。
放置せず、早めに解体や売却を検討することが大切です。