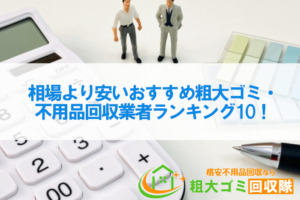だるまの処分の仕方7選!供養のタイミングと方法も解説!

この記事では、だるまを処分する7つの方法と、供養のタイミングや注意点について詳しく解説します。
古くから縁起物として親しまれているだるま。
願いを込めて目を入れただるまは、目標達成や願望成就のシンボルとして、多くの人々に愛されています。
しかし、願いが叶ったり、古くなっただるまを処分する際には、どのようにすれば良いのか悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事を読めば、だるまの処分方法や作法についてわかるようになります。
だるまの処分の仕方7選

だるまを処分する方法は大きく分けて7つあります。
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
神社や寺院で供養と処分を頼む
だるまを処分する最も一般的な方法は、神社や寺院に持ち込んで供養してもらうことです。
多くの神社や寺院では、だるま供養と呼ばれる儀式を行い、お焚き上げによって処分してくれます。
だるま供養は、一年を通していつでも行うことができますし、だるまに感謝の気持ちを伝えられる処分方法です。
お焚き上げの際には念珠や数珠を持参する人もいます。
また通年の供養だけではなく、年末年始やお盆などの時期に特別のだるま供養を行っているところがあります。
日本の伝統に触れたいという方には、タイミングを合わせて神社や寺院で供養と処分を頼むのもよいでしょう。
だるま供養の費用は、神社や寺院、だるまの種類や大きさによって異なりますが、一般的には、数百円から数千円程度です。
だるまとは?歴史的背景から解説
だるまは、日本における縁起物の代表格で、主に願掛けや開運を祈願するために使われる張り子(紙製)の人形です。目が描かれていない状態で販売され、願いを込めて片目を入れ、願いが叶ったらもう一方の目を入れるという習わしが広く知られています。
歴史的背景と起源
禅宗と達磨大師
だるまの名前の由来は、達磨大師(ダルマ)という人物にあります。彼は6世紀ごろのインドの仏教僧で、中国禅宗の開祖とされる重要な人物です。
伝説によれば、達磨大師は中国に渡り、少林寺で9年間壁に向かって座禅をし続けたとされます。その修行姿が、手足を使わない座禅の姿=だるま人形の形へとつながっています。
江戸時代の発展
現在のようなだるまが日本で広く普及したのは江戸時代中期です。特に群馬県高崎市の少林山達磨寺が有名で、農家が冬場の副業として作り始めた張り子のだるまが、庶民の間で「福だるま」として定着しました。
高崎だるまは「七転八起」の意味を込めて、転んでも起き上がる縁起物として親しまれています。
形・色・目の意味
- 形状:下が重くて起き上がる「起き上がりこぼし」の構造で、困難があっても立ち直る象徴です。
- 赤い色:もとは病除けの色とされ、疫病退散の願いが込められていました。現在では商売繁盛や家内安全の色ともされています。
- 目入れ:願いを込めて片目を入れ、叶ったら両目を入れるという習慣は、仏教の「開眼供養」がルーツとされています。
現代におけるだるまの役割
政治家の選挙、企業の事業成功祈願、受験生の合格祈願など、さまざまな場面で使用されており、「願いを形にして見える化する」という点で現代人の心理にも合致しています。
宗教学や民俗学の視点から見ると、だるまは「信仰」と「民間習俗」が融合した存在であり、自己実現への心理的サポート装置としても機能しています。願掛けという行為を通じて、目標意識を明確にし、継続的な努力を促すという点で、日本文化における“心の道具”と言えるでしょう。
どんど焼きで処分する
どんど焼きは、小正月の時期に行われる伝統行事であり、古いお正月飾りやだるまを燃やして、神様へ感謝の気持ちを伝え、五穀豊穣や無病息災を祈願するものです。
地域によって呼び方や内容は異なりますが、だるまを供養するという意味合いは共通しています。
どんど焼きは、古くから続く日本の伝統行事です。だるまを燃やすことで、地域の伝統文化に触れることができ、多くの場合は、無料でだるまを燃やすことができます。
だるまをきれいにして、どんど焼きの炎を通じて、だるまに感謝の気持ちを伝えて、だるまが燃え尽きるまで、その場で見守るようにしましょう。
どんど焼きとは?〜正月のしめくくり、日本の伝統行事〜
お正月が終わるころ、日本各地で「どんど焼き」という行事が行われます。竹や木で組んだ大きなやぐらを作り、そこにお正月飾りや書き初め、古いお守りなどを集めて燃やすお祭りです。火が大きく燃え上がる様子はとても迫力があり、冬の空に赤い炎が美しく映えます。
どんど焼きには、いくつかの意味があります。
- 歳神様(としがみさま)を空へお送りするため
お正月に家へ迎えた歳神様を、火の煙にのせて天へお帰しするという意味があります。 - 無病息災(むびょうそくさい)を願う
燃やした火にあたったり、煙を浴びると、一年元気に過ごせると言われています。 - 書き初めが上達するように
お正月に書いた書き初めを火にくべると、字が上手になるとも伝えられています。
地域によっては、火で団子やお餅を焼いて食べる風習もあります。どんど焼きの火で焼いたものを食べると、一年健康に過ごせると信じられています。子どもたちにとっては、この焼き団子やお餅が大きな楽しみのひとつです。
どんど焼きは、地方によって呼び名や行い方が少しずつ異なります。「左義長(さぎちょう)」「どんと祭」「鬼火焚き」など、いろいろな名前で呼ばれているところもあります。
どんど焼きは、お正月を締めくくり、新しい一年の幸せや健康を願う、日本ならではの大切な行事です。
だるま市で処分する
だるま市は、古いだるまを買い取ってもらい、新しいだるまを購入することができる、主に正月から3月にかけて各地で開催されるイベントです。
地域によって開催時期や規模は異なりますが、だるまを供養するという意味合いは共通しています。
ただし、だるま市は、年に数回かつすべての地域で開催されているわけではなく、壊れただるまは、持ち込むことができないので注意が必要です。
だるま市ってどんなイベント?
だるま市とは、日本各地で開催される縁起物「だるま」の市(いち)であり、特に年始や節分、旧正月などの時期に合わせて開催されることが多い伝統行事です。だるまは「起き上がりこぼし」の形状で、転んでも起き上がることから「七転び八起き」の象徴として、開運・商売繁盛・家内安全・学業成就などを願う縁起物とされています。
だるま市の最大の目的は、前年に願掛けをしただるまを納め、新しいだるまを購入することです。多くの会場では、古いだるまをお焚き上げ(供養)し、僧侶による祈祷が行われた新しいだるまが販売されます。訪れる人々は、購入しただるまに片目を入れて願い事を託し、願いが成就した際にもう片方の目を入れるという風習に従います。
市では大小さまざまなだるまが並び、赤色が主流ですが、金色や白色、青色などカラーバリエーションも豊富で、それぞれの色に意味が込められている場合もあります。また、だるまの眉毛が鶴、髭が亀の形に描かれている「鶴亀だるま」など、地域ごとに特徴的なデザインも見られます。
さらに、だるま市では以下のような催しも行われます:
- お焚き上げ式(古だるま供養)
- 僧侶による護摩焚き祈願や読経
- 露店の出店(食べ物、縁起物、雑貨など)
- 和太鼓や地元芸能のパフォーマンス
代表的なだるま市には以下のようなものがあります:
- 少林山七草大祭だるま市(群馬県高崎市)
毎年1月6日〜7日に開催。日本最大のだるま生産地・高崎市のシンボル的な行事で、200以上の露店が並び、全国から20万人以上が訪れます。だるまの発祥の地ともいわれる少林山達磨寺にて開催され、祈祷だるまが有名です。 - 深大寺だるま市(東京都調布市)
毎年3月3日・4日に開催。江戸時代から続く伝統行事で、境内には数百のだるま店が並び、僧侶による「開眼法要」が特徴です。願いが叶うとされる「目入れ」もこの法要で行われます。 - 高尾山薬王院だるま市(東京都八王子市)
節分会と合わせて2月初旬に開催。参拝客は山上の薬王院でだるまを授かり、特設火炉で古いだるまを供養します。節分の豆まき式と合わせて多くの参拝客で賑わいます。 - 勝田全国だるま市(茨城県ひたちなか市)
毎年1月中旬に行われ、勝田駅前通りが歩行者天国となり、約300店以上の露店が並びます。だるまだけでなく、地元グルメも楽しめる市として有名です。
だるま市は、ただの物販イベントではなく、人々の願いや信仰、地域の伝統文化が融合した年の始まりを彩る大切な風物詩です。
人形供養祭で処分する
人形供養祭は、人形やぬいぐるみなどを供養するイベントです。
地域によって呼び方や内容は異なりますが、だるまを供養するという意味合いは共通しています。
基本的には、だるま市と立ち位置は同じようなイベントで、神社や寺院で行われることが多いですが、近年ではイベント会場や商業施設などで開催されることも増えています。
人形供養祭は、通年開催ではなく、年に数回しか開催されません。
人形供養祭は、古くから続く日本の伝統行事です。
だるまを供養することで、地域の伝統文化に触れることができます。
人形供養祭とは?
人形供養祭とは、不要になった人形やぬいぐるみに感謝の気持ちを込めて供養し、お焚き上げ(お守り、人形、だるま、写真、遺品などの思いがこもったものをただの「ゴミ」としてではなく、感謝の気持ちを込めて焚いて供養する)する宗教的な儀式です。長年大切にしてきた人形には、思い出や愛着が宿っていると考えられており、単にゴミとして処分するのではなく、丁寧に送り出したいという日本人の心情から、この文化が根付いています。
この供養は、全国各地の寺院や神社で開催されており、定期的な「人形供養祭」として広く知られています。神職や僧侶による読経・祝詞(のりと)を通じて、人形に宿る魂を鎮め、浄化し、最終的にはお焚き上げによって天に還すという流れが一般的です。
以下は、具体的な代表的な人形供養祭の例です:
- 淡嶋神社(和歌山県加太)「雛流し・人形供養」
毎年3月3日に行われる「雛流し」は有名で、全国から人形が集まります。人形たちは舟に乗せられ、海に流されて供養されます。人形供養は年間を通しても受け付けられており、郵送も可能です。 - 本妙寺(東京都豊島区)「人形供養祭」
毎年10月に開催されるイベントで、持ち込まれた人形に対して僧侶が読経を行い、魂を抜いたあと丁寧に焼納されます。ぬいぐるみや雛人形など、種類を問わず受け入れています。 - 市谷亀岡八幡宮(東京都新宿区)「人形感謝祭」
毎年10月の第2日曜日に開催。神道形式で、神職が祝詞を奏上し、持ち込まれた人形に感謝を捧げます。供養後は丁寧に焼納されます。 - 高野山東京別院(東京都港区)「人形供養大祭」
毎年9月に行われる大規模な供養祭で、多くの人々が参列します。人形だけでなく、写真や手紙なども供養の対象とされています。
参加方法としては、当日会場に直接持ち込むほか、郵送での受付も可能な場合が多いです。供養料(志納金)は、だいたい1箱あたり1,000円~5,000円ほどが目安で、会場によって異なります。
人形供養祭は、人と人形との絆を大切にし、「ありがとう」という思いを形にする、日本独自の優しい文化です。大切な人形を手放す際の心の区切りとして、多くの人が利用しています。
自治体のゴミ回収に出す
自治体の粗大ゴミ回収を利用してだるまを処分することも可能です。
だるまを自治体のゴミ回収で処分する際の手順は、地域ごとに異なりますが、以下のような一般的な流れがあります。
① だるまが「可燃ごみ」として処分できるか確認
多くの自治体では、だるまは木製や紙製であることが多く、「可燃ごみ(燃やせるごみ)」として出すことが可能です。ただし、サイズや素材によって分類が異なる場合もあるため、必ずお住まいの自治体の公式ホームページや「ごみ分別表」で確認してください。
② 必要に応じて「魂抜き」「供養」を検討
だるまは縁起物・祈願成就の対象であるため、処分前にお焚き上げや供養を望む方もいます。そういった場合は、地域の寺社で実施されている「人形供養」や「だるま供養祭」への持ち込みがおすすめです。供養後、寺社側で適切に処分してくれる場合もあります。
③ ゴミ袋に入れる際の注意
可燃ごみとして処分する場合は、以下の点に注意してください。
・指定のごみ袋を使用する
・ガラス製の目が付いている場合は、外して「不燃ごみ」へ
・燃えにくい素材(プラスチック製・金属部品ありなど)は不燃ごみや粗大ごみに分類されることもある
④ ごみ収集日に出す
決められた可燃ごみの収集日に、地域のルールに従ってごみ集積所に出します。だるまの目などが剥がれている場合、怪我の防止のため紙などで包んでから袋に入れるとよいでしょう。
⑤ 心配な場合は自治体に問い合わせ
処分方法に迷う場合は、自治体の清掃課やごみ処理センターに直接問い合わせるのが確実です。
フリマサイトなどで売却する
まだ使える状態のだるまであれば、フリマサイトなどでも一定の需要はあるので、売却することも可能です。
ただし、希少なだるまや、状態の良いだるまであれば、売却できる可能性がありますが、傷みが激しいものや目玉を塗ったものは売却できない可能性が高まります。
出品にあたっては、だるまの状態を正直に説明しないと、購入者との間でトラブルが発生する可能性がありますし、掲載する写真にも見栄えや、状態を正確に伝えられるようにする必要があります。
また、だるまの状態や相場を考慮して、適切な価格を設定しましょう。
購入者が現れた時には、だるまを破損しないように、丁寧に梱包し、購入者とのやり取りは丁寧に、迅速に対応するようにしてください。
不用品回収業者に依頼する
不用品回収業者に依頼すれば、自宅からだるまを持ち出す必要がなく、手軽に処分することができます。
ただし、業者によって料金は異なりますが、粗大ゴミ回収や自治体のゴミ回収よりも高額になる場合が多いため、だるまの他にも不用品がある方にはおすすめの方法です。
不用品回収業者へ依頼する際には、事前に料金を明確にしていない業者や、高額な料金を請求する悪徳業者も存在するため、業者選びに注意するようにしてください。
業者選びには、複数の業者から見積もりを取ったり、行政からの許可を得ている業者かを確認したり、業者の口コミや評判を確認したりすることで、悪徳業者を避けられます。
契約内容をよく確認し、キャンセル条件や違約金などを理解した上で契約しましょう。
信頼できるおすすめ不用品回収業者ランキングトップ10は以下の記事で紹介しているので、こちらも参考にしてみてください。
だるまは供養してから処分するのが一般的

だるまは単なる置物ではなく、中に神様が宿ると考えられています。
そのため、願いが叶ったり、古くなっただるまを処分する際には、感謝の気持ちを込めて供養してから処分するのが一般的です。
だるまを処分するタイミング

だるまを処分するタイミングについて、3つのタイミングを解説していきます。
願いが無事叶ったとき
願いが叶ったときは、だるまを処分する最も一般的なタイミングです。
古くから願いが叶ったら、だるまに目を入れて、感謝の気持ちを込めて供養した上で、処分するという習わしがあります。
また、願いが叶った後は、新たな目標を設定して、新しい願いを込めた新しいだるまを用意しましょう。
一方で、願いが叶わなかった場合は、処分することで、運気を好転させると考えられています。
古いだるまは、古くなった運気を象徴していると言われています。
ご利益の期間が過ぎたとき
だるまのご利益期間は一般的に5年と言われています。
5年経過しただるまは、新しい願いを込めた新しいだるまに置き換えるタイミングです。
だるまは、時間が経つにつれてご利益は弱まり、古くなった運気を纏ってしまうため、その古くなった運気をリフレッシュし、新たな運気を呼び込むために処分する必要があるとされています。
5年が過ぎたタイミングで新しいだるまを購入することで、自身の目標を明確にし、新たな一歩を踏み出すきっかけにしてください。
また、5年が過ぎると、だるまの色褪せや破損などが見られることも少なくありません。見た目が損なわれただるまは、せっかくの願いにも悪影響を及ぼす可能性があります。
遺品整理で古いだるまを見つけたとき
遺品整理で古いだるまを見つけた場合は、故人の意思を尊重し、適切に処分する必要があります。
故人がだるまについて何か言っていたか、遺書などに記されていないかを確認しましょう。特に思い入れのあるだるまであれば、供養して大切に保管しておきたいという希望があったかもしれません。
故人の意思が見当たらない場合は、ご利益の期間が過ぎているため、運気の面からも処分を検討しましょう。
自宅で供養する場合は、清めの塩でだるまを清め、感謝の気持ちを込めて処分しましょう。
遺品整理で困っている方は、口コミの評判が良いおすすめの遺品整理業者を5社ピックアップして紹介しているので、こちらも参考にしてみてください。
だるまの回収処分なら「粗大ゴミ回収隊」もおすすめ!
だるまの処分方法について7つ紹介しました。
だるまをそのまま処分してしまうと、バチが当たると言われているため、塩などで清めた上で処分するようにしましょう。
不用品回収業者はだるまだけではなく、不用になった家電製品や処分できずに眠っていた大きな不用品などもまとめて回収します。
他に不用品がないかも確認の上、だるまの処分のタイミングで不用品が溜まっている方にはおすすめです。
だるまの回収・処分はぜひ「粗大ゴミ回収隊」にご相談ください。
 に
にまずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531 お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
にまずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

 に
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531 お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
に
 に
にまずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

処分でよくある質問
- 作業完了後にお支払いが可能
- 一括払い・分割払いから選べる柔軟な決済方法
- 信販会社との契約による安心・透明な仕組み
- 見積書にはクーリングオフの記載もあり、消費者保護が万全
- 部品やタイヤのサイズや数量によって料金が変動する場合がある
- オイルやバッテリーなどの液体を含むものは、回収可否が異なることがある
- 重量物の場合、搬出の際に追加費用が発生することがある
- 退去日が迫っており、早急に回収してほしい
- 搬出経路が狭く、自分では運び出せない
- 解体や分別が必要で作業が大変
- 他の不用品もまとめて回収してほしい
- お問い合わせ: 粗大ゴミ回収隊のサイトよりお問い合わせいただけます。
- 見積もり: 現地にて実際に回収する品物を確認し、見積もりを行います。
- 回収作業: 承認いただいた後に、安全かつ迅速に回収作業を進めます。
- 費用のお支払い: 作業完了後、ご指定いただいた方法でお支払いをお願いいたします。
Q 後払い決済対応は可能ですか?
はい、可能です。後払い決済をご希望の際は、以下の流れに従ってご対応させていただきます。
粗大ゴミ回収隊では、後払い・分割払いが可能です。
「今すぐ片付けたいけれど、手元に現金がない…」そんな場合でもご安心ください。
当社では、信販会社ライフティ株式会社の後払い決済サービス「WEぶんかつ」をご利用いただけます。
サービスの特徴
事前に「後払いを希望」とお伝えいただくだけで、手続きもスムーズに進められます。
回収サービスを安心してご利用いただけるよう、当社がしっかりサポートいたします。
Q ガレージに保管していた古タイヤや車部品の処分も対応していますか?
ガレージに保管していた古タイヤや車部品の処分も対応していますか?
はい、自家用車の不要部品や古タイヤ、工具類も回収可能です。
特にガレージに長年保管していた古タイヤやホイール、バッテリー、車のパーツなどは、処分方法に悩まれる方が多いですが、粗大ゴミ回収隊ではこれらの回収にも対応しています。内容によっては別途料金が発生する場合がございますので、以下のような点を事前にご確認いただくと安心です。
もし処分をご検討中の場合は、回収品の種類や量、保管状況などを詳しくお聞かせいただけますと、より正確なお見積もりが可能です。お手数ではございますが、ぜひ一度粗大ゴミ回収隊の公式サイトからお気軽にお問い合わせください。スムーズな回収のご案内をさせていただきます。
Q 引っ越しに合わせて壊れたベッドフレームだけ処分したいです
壊れたベッドフレームの回収について
はい、壊れたベッドフレームの回収も承っております。分解作業も含めてお任せいただけますので、重くて処分が難しい家具も安心してお任せください。
引っ越しに伴うベッドフレーム処分をご検討の方へ
引っ越しを機に、壊れたベッドフレームだけを処分したいというご相談も多くいただきます。粗大ゴミ回収隊では、以下のようなご事情にもしっかり対応しております。
ベッドフレームはサイズが大きく重量もあるため、処分する際は搬出の安全性や解体の手間が問題になることが多いですが、当社ではスタッフが分解から運び出しまで対応いたします。女性の一人暮らしやご高齢の方など、お一人では作業が難しい場合も安心です。
お見積もりやお問い合わせについて
粗大ゴミ回収隊では、お見積もりは無料で承っております。また、急なご依頼にも柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは、粗大ゴミ回収隊の公式サイトをご覧いただけますと、サービス内容や料金の目安をご確認いただけます。
引っ越しをスムーズに進めるためにも、壊れたベッドフレームの処分でお困りの際は、ぜひご相談くださいませ。
Q エアコンの配管ホースや金具だけの処分もできますか?
エアコン解体後の部品回収について
エアコン取り外し後に残った配管ホースや金具などの部品は、当社が丁寧に回収いたします。小さなパーツでも見逃すことなく、お客様のご要望に応じたサービスを提供しますので、ご安心ください。
よくある質問:配管ホースや金具だけの処分も可能ですか?
はい、可能です。不用品回収の専門業者として、エアコンの配管ホース、金具、ネジなどといった小さな部品まで、しっかり回収・処分いたします。こちらの作業は頻繁にご依頼いただく内容であり、経験豊富なスタッフが対応していますので、安心してお任せください。
不用品回収の流れ
さらに安心の不用品回収サービス
私たちは、お客様の疑問や不安を解消しながら、プロの視点で最適なサービスを提供しています。不用品回収に関する詳細や料金について知りたい方は、ぜひこちらをご覧ください。