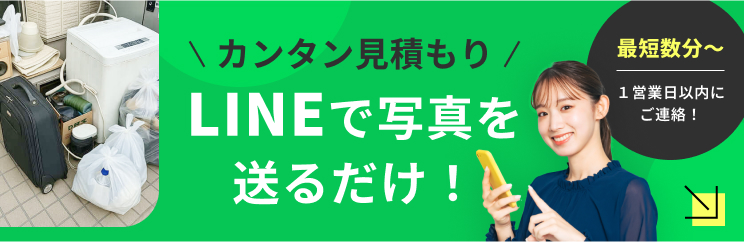ためこみ症はゴミ屋敷につながることも?生活の工夫や片付け方・対策

この記事では、「ためこみ症(ホーディング症)」の特徴や背景、捨てられない物の傾向、放置による生活リスクについて解説します。
さらに、片付けを進めるための工夫や実際の事例、自力での対処と専門業者への依頼の違いも紹介します。
ためこみ症は米国精神医学会の診断基準(DSM-5)にも記載された精神疾患の一つであり、気づかれにくい反面、生活や人間関係に大きな影響を及ぼす可能性があります。
本記事を読むことで、自分や家族の状況を理解しやすくなり、片付けを始めるきっかけや支援の選択肢が見つかるはずです。
また、必要に応じて医療機関や専門業者の支援を利用する方法についても触れています。
「片付けられないこと」に悩んでいる方や、身近な人の様子が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、診断や治療を行うものではありません。心身の不調や生活への影響に不安がある場合は、必ず医師など専門機関にご相談ください。
目次
ためこみ症とは
ためこみ症(Hoarding Disorder)は、不要な物を過剰にため込み、捨てられない状態が慢性的に続く精神医学的に認められた障害です。
単なる「片付け下手」や「性格の問題」とは異なり、生活の質や健康、安全に深刻な影響を及ぼすことがあります。アメリカ精神医学会の診断基準 DSM-5 においても、独立した診断名として位置づけられています。
ためこみ症の特徴
ためこみ症の人は、新聞や雑誌、衣類、壊れた家電など、本来不要になった物を捨てられずにため込み続ける傾向があります。
「いつか使うかもしれない」「捨てるのはもったいない」と考えて処分を先延ばしにし、生活空間が物であふれ、動線を塞いでしまうことも少なくありません。その結果、住環境が衛生的に悪化し、ゴミ屋敷化へと発展するケースも報告されています。
参考:International OCD Foundation(国際強迫症財団)
ためこみ症の背景にある考え方
ためこみの背景には、心理的・行動的な要因が複雑に絡み合っています。物を捨てることに強い不安や罪悪感を抱き、必要と不要の判断そのものが難しい人も少なくありません。
また、物を所有することで安心感やコントロール感を得るケースや、衝動買い・収集癖によって物が増え続けることもあります。こうした心理的要因が積み重なり、片付けられない状態が悪化するのです。
参考:
NHS(英国国民保健サービス)
ためこみ症の発症傾向
ためこみ症の有病率は、国内外の研究で人口の約2〜6%と報告されており、日本の精神科領域の文献でも同様の傾向が示されています。
この割合は決して稀ではなく、誰にでも発症し得る身近な問題といえます。
発症時期としては、思春期から20代で兆候が現れやすく、その後、年齢とともに慢性化する傾向があることが指摘されています。そのため、若い頃に軽度の症状が見られても、放置すると高齢期に深刻化しやすいとされています。
また、性差については「男性、女性ともに同じ」という研究もあれば、「女性より男性にやや多い」とする研究もあり、発症の背景や進行パターンには一定の傾向があるものの、男女どちらも発症する可能性があると考えたほうがよさそうです。
参考:
DSM-5(米国精神医学会)
米国国立精神衛生研究所(NIMH)
Mayo Clinic
厚生労働省
※ためこみ症は、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)において、強迫症や不安症とは独立した診断カテゴリーとして明確に定義されています。
補足|ためこみ症の有病率
「有病率(prevalence)」とは、簡単に言えば、有病率 = その時点で病気を持っている人の“割合” です。ある集団(たとえば人口全体、ある年代層など)において、一定時点あるいは一定期間内にその疾患(ここでは「ためこみ症/hoarding disorder」)の診断基準を満たす人の割合を指します。
「ためこみ症」あるいは「hoarding disorder」がどの定義・診断基準を用いるかで、有病率の推定値は変わり得ます。たとえば、症状の重症度、日常生活への支障の程度、自己報告 vs 面接調査、無症候者も含めるかどうか、などがバラつきを生む要因です。
時点有病率 or 生涯有病率 or 症状保有者率
多くの文献で扱われる「有病率」は「時点有病率(ある時点で基準を満たす割合)」であり、生涯でその基準に達した率(生涯有病率)はより高く出る可能性があります。たとえば、日本のある情報では「生涯有病率は 14%」とするものもあります。
多くの疫学研究は欧米を対象としており、文化・居住環境・住宅事情などが異なる国では実際の割合も変動する可能性があります。国内で精密な全国調査がなされている例は限られています。
実際、国内の精神医学・臨床心理学文献で「ためこみ症」の全国疫学調査を明確に示すものは、今回執筆する上で調査・確認した範囲では見つかりませんでした。
しかし、「ためこみ症」の傾向があっても本人が病識を持たない(自覚がない)こと、診療を受けないことも多いため、実際の潜在的な割合は報告値を上回る可能性があります。
ためこみ症によく見られる品目
ためこみ症の事例では、以下の品目が居住空間を圧迫している様子がよく見られます。
衣類やファッション小物
ためこみ症の方は、着なくなった服や使わなくなったファッション小物を「いつか着る」「いつか使う」と考えて手放せない傾向があります。
サイズが合わなくなったり、素材が劣化しても捨てられず、服やバッグが増え続け、本来の収納スペースでは収まりきらなくなります。やがて整理整頓が難しくなり、必要な衣類や小物が埋もれて見つからない状態に陥りやすくなります。
さらに、湿気のこもりやすい環境ではカビや害虫が発生し、悪臭やアレルギーのリスクを高めるなど、健康被害にもつながります。
どのような人が該当しやすいか
心理学・医学的な研究によれば、以下のような特徴を持つ人が「衣類やファッション小物」をため込みやすいとされています。
- 完璧主義傾向の強い人:衣類を「まだ使える」「高価だったから捨てるのはもったいない」と考えやすい(米国国立精神衛生研究所(NIMH))。
- 不安症やうつ傾向を抱える人:衣服を保持することで心理的な安心感を得ようとし、処分が不安につながる(Mayo Clinic)。
- 衝動買いや収集癖がある人:買い物依存傾向から衣服が増え続け、結果的に生活空間を圧迫する(NHS)。
これらの要因が重なることで、日常生活に支障をきたすレベルで衣類をため込んでしまうケースがあります。ためこみ症は単なる「片付け下手」ではなく、精神的背景に根ざした問題であるため、早期の理解と専門的支援が重要です。
雑誌・本・紙類
雑誌や本だけでなく、チラシやダイレクトメールなどの郵便物をため込みやすい傾向が、ためこみ症の事例でしばしば報告されています。
紙類はかさばるだけでなく重量もあるため、処分に労力がかかりやすく、整理を先延ばしにしてしまう傾向が指摘されています。その結果、読み返すことのない本や資料で生活空間が圧迫され、大切な書類との区別が難しくなるなど、日常生活に支障を及ぼす場合があります。
心理学的には「情報を失うことへの不安」や「いつか役立つかもしれない」という思考が背景にあるとされ、こうした心理的要因が紙類の過剰な保存につながると考えられています(米国国立精神衛生研究所)。また、分類や決断が苦手な人ほど紙類を溜め込みやすいとされ、これは実行機能(判断や整理整頓に関わる脳の働き)の弱さとも関連があると報告されています(NHS)。
さらに、紙類を長期間放置することで害虫やカビの発生源になるリスクがあるため、健康上の問題にもつながり得る点が注意されています(厚生労働省)。
食品や日用品のストック
ためこみ症の事例では、食品や日用品を過剰にストックしてしまう傾向がしばしば報告されています。
ストックが多すぎると管理が追いつかず、賞味期限切れの食品が放置されたり、在庫があるにもかかわらず買い足してしまったりすることがあります。家庭の整理を行った際に、数年前に期限が切れた食品や、経年劣化したタオル・洗剤、さらにはカビの生えた食器などが見つかるケースも確認されています。
背景にある心理・行動的要因
- 安心感を求める傾向:日用品や食材を「備蓄しておけば安心」と考え、必要以上に買い込む(NIMH)。
- 買い物依存や強迫的購買行動:安売りや特売をきっかけに衝動的に購入し、結果として在庫が膨らむ(NHS)。
- 判断力や実行機能の低下:特に高齢者では「必要かどうかの判断」や「適切な在庫管理」が難しくなり、ためこみを助長する(Mayo Clinic)。
このような環境では、食品や日用品が無駄になるだけでなく、害虫やカビの温床となり、健康被害につながるリスクも指摘されています(厚生労働省)。
古い家電や壊れた生活用品
壊れた家電や使わなくなった家具・生活用品を処分できずに残してしまう傾向が、ためこみ症の事例ではしばしば報告されています。
新しい製品を購入しても古い物を手放せないため、生活空間が次第に圧迫されていきます。家電や家具は大きなスペースを必要とするため、室内に収まりきらず屋外にまで放置されるケースも確認されています。
医学的・心理学的な背景
- 「いつか修理して使えるかもしれない」という思考:壊れていても将来使える可能性を過大に評価し、処分を先延ばしにする(NIMH)。
- 愛着や思い出の投影:古い家電や家具を「思い出が詰まった物」として扱い、処分することに強い心理的抵抗を感じる(Mayo Clinic)。
- 実行機能の低下:高齢者や認知機能の衰えがある人では、「処分する判断」や「片付けの計画立て」が難しくなり、壊れた物が積み重なりやすい(NHS)。
具体的な事例としては…
- 壊れた冷蔵庫を「修理すれば使える」と考え、ベランダや玄関先に放置したまま数年経過する。
- 動かなくなったテレビやパソコンを「部品が役立つかもしれない」と保存し続け、結果的に複数台が積み上がる。
- 座面が壊れた椅子や机を「思い出があるから」と捨てられず、生活動線を塞いでしまう。
このような状況は生活空間を狭めるだけでなく、転倒リスクや害虫発生の温床になるなど、健康や安全面でのリスクも高めると指摘されています(厚生労働省)。
思い出の品や写真
写真や手紙、プレゼントの包装紙など、感情が深く結びついた品々は、誰にとっても処分に迷うものです。
ためこみ症の傾向がある方では、映画やコンサートのチケット、包装紙やリボン、小学校の作品などといった一見些細な物でも捨てられないといった事例が多く報告されています。
このような物品は整理分類が難しいことも多く、保管スペースに無造作に積み重なっていく傾向が見られます。その結果、かえって本来大切にしたい思い出の品の保存状態が悪化するという皮肉な状況にもつながることがあります。
背景にある心理・医学的特性
- 喪失への強い不安:思い出の品を捨てること=過去を失うことと捉え、強い不安や悲しみを感じてしまう(NIMH)。
- 感情調整の困難:物に感情を強く投影する傾向があり、それを手放すことで精神的なバランスが崩れることを恐れる(NHS)。
- 実行機能や判断力の弱さ:感情と論理のバランスを取りにくく、分類や取捨選択が困難になる傾向がある(Mayo Clinic)。
該当しやすい人は…
- 大切な人との別れを経験したばかりの人:亡くなった親やペットの写真や持ち物をすべて保管し、手放すことで「忘れてしまうのでは」と感じてしまう。
- 孤独を感じやすい高齢者:昔の手紙や年賀状、卒業アルバムなどを繰り返し読み返す一方で、処分できずに保管が積み重なる。
- 愛着障害の傾向を持つ人:人とのつながりを物に置き換える傾向があり、感情的記憶が宿るモノへの執着が強まる。
このような傾向は感情と記憶が深く関係するため、専門的な理解と支援が必要です。放置すれば住環境の悪化につながるほか、大切な記憶そのものを損なってしまうリスクもあると指摘されています(厚生労働省)。
ためこみ症を放置するリスク
ためこみ症を放置すると、住環境の劣化だけでなく健康被害や社会生活における不安、金銭的な負担などのリスクも積み重なっていきます。
対処が遅れるほどに問題は深刻化し、解消するために要する労力や時間、費用負担も増大するものです。
以下に、ためこみ症の放置によって発生し得るリスクについて解説します。
部屋がゴミ屋敷化する
捨てられずにためこむ生活を続けていると、ゴミ屋敷化して以下のように多くの問題を引き起こします。
- 生活動線が悪くなる
- 掃除や換気、片付けが困難になる
- 本来の居住スペースが確保できなくなる
- 害虫や悪臭が発生する
生活スペースや収納スペース、ゴミ置き場の境界線がなくなれば、通路や出入り口も塞がれ、屋内の移動や火災発生時などの避難も困難です。
害虫や悪臭の発生も懸念されます。
家中に雑多な物やゴミが無秩序に積み上げられるような状況では、テーブルやベッドなどの生活スペースが本来の用途で利用できなくなり、基本的な生活環境を維持できません。
生活や健康に支障が出る
ためこみ症を放置していると、ホコリやカビ、害虫などの発生により不衛生な環境となり、以下のように生活や健康に支障をきたす可能性があります。
- アレルギーや呼吸器系疾患の発生・悪化
- 障害物による転倒事故
- 火災発生時の逃げ遅れ
- 臭いや害虫発生による不快感
- 自立性の低下
生活環境や健康状態が悪化すれば片付けも進まなくなり、さらなる悪循環に陥る可能性があります。
人間関係や近隣トラブルにつながる
ためこみ症の方は「だらしがない」「怠けている」などと誤解されやすく、家族や同居人との摩擦の原因となるケースが多く見られます。
ゴミ屋敷化して臭いや害虫が発生すれば、近隣住民からの注意や苦情、訴訟トラブルにまで発展する可能性もあるでしょう。
地域的な問題となれば、ゴミ屋敷条例などをもとに、自治体の指導や介入に至る可能性も否定できません。
ためこみ症は人間関係を悪化させるだけでなく、信用を低下させ、周囲からの理解を得られずに孤立化するなどの影響も懸念されます。
金銭的な負担が増える
ためこみ症で家がゴミ屋敷化し、業者などに処理を依頼することとなれば、以下のような費用負担が発生します。
- 片付け費用
- 不用品処分費用
- 清掃費用
- 害虫駆除費用
- リフォーム・修繕費用
近隣住民とのトラブルに至っているケースでは、引っ越しが必要になったり、賠償金を請求されたりするケースも考えられます。
孤立や自己嫌悪など心理的負担が増す
ためこみ症による社会的孤立は、精神的負担や不安感を増大させる可能性があります。
恥ずかしさや自己嫌悪感から、周囲への相談や支援を求めにくくなり、問題解決が遅れて悪循環に陥る可能性があります。
環境改善が進まないうえ、対人関係にも悪影響を及ぼすため、回復への大きな障壁となるでしょう。
ためこみ症の片付けのコツ
ためこみ症の方が、抵抗感なくスムーズに片付けを進めるのは、周囲が考える以上に難しいことです。
生活習慣や判断基準を見直し、適切な取り組みを積み重ねていくことが重要です。
以下のコツを押さえて、段階的に片付けを習慣化しましょう。
物を増やさないルールを作る
ためこみ症の方は、処分するハードルが高い傾向があるため、まずは物を増やさないように心がけましょう。
例えば、以下のようなルール作りが有効です。
- 無料でも使わない物は断る
- 新しい物を1点購入する際は、3つ以上の物を処分する
- 買い物リストに記載した物以外は購入しない
- 決まったスペースに置ける範囲でのみ、追加購入を検討する
処分できずに物を増やしていれば、家に物があふれて管理が行き届かなくなります。
管理できる範囲内でルールを設定すれば、効率的に片付けられます。
手放すタイミングを決めておく
ためこみ症の方は、物の処分が苦手です。処分への抵抗感を抑えるために、手放すタイミングのルール化をおすすめします。
例えば、以下のようなルール決めをすると効果的です。
- 1年以上使用しなかった物は処分する
- 欠けやヒビのある食器は処分する
- 同じ用途の物は、いずれか1点のみを残してあとは処分する
仕分けを習慣化する
ためこみ症を解消するために、以下の仕分けを習慣化しましょう。
- 必要な物
- 不要な物
- 判断を保留する物
不要物としての仕分けが難しい場合でも、保留であれば分類しやすくなります。
保留にしたものは日付を記入し、例えば「このシーズンに一度も使用しなかったら処分する」などとルールを決めましょう。
日常的に習慣化していくと、仕分けへの抵抗感が薄れて処分へのハードルが下がり、環境改善に向けて取り組みやすくなります。
必要に応じて専門業者に依頼する
ためこみ症で自力での片付けが難しい場合は、専門業者に相談してみましょう。
専門業者はプライバシーに配慮しながら、迅速に対応してくれます。
定期的に業者に片付けをサポートしてもらえば、ゴミ屋敷化を未然に防げます。
業者を選ぶ際は許認可を受けているか確認のうえ、2~3社に相見積りを依頼しましょう。
費用やサービス内容、対応力などの比較検討に役立ちます。
自力での片付けと業者依頼の比較
ためこみ症でゴミ屋敷となった家の片付けを、自力で済ませるか業者に依頼するかで迷う方もいるでしょう。
以下のとおり、それぞれにかかる費用や労力、時間には大きな違いがあります。
| 項目 | 自力で片付ける | 業者に依頼する |
|---|---|---|
| 費用 | 基本的に無料 ※処分費用のみ |
・1K/1R:3.2万円~10万円 ・2DK〜3DK:8.2万円~25万円 ・一軒家:20万円~(※) |
| 作業時間 | 数日〜数週間かかることも | 半日〜1日で完了するケースが多い |
| 体力・労力 | 大きな家具や大量のゴミは負担大 | 搬出や分別もすべて任せられる |
| 精神的負担 | 思い出の品を手放す決断が難しい | 第三者が介入することでスムーズに進む |
| メリット | ・費用を抑えられる ・自分のペースでできる |
・最短で片付けてくれる ・ストレスが少ない |
| デメリット | ・作業が進まず挫折しやすい ・再発の恐れ |
・費用がかかる ・信頼できる業者選びが必要 |
※2025年8月100社の独自調査による(床からの高さ50cm未満の場合)
自力で片付けができれば費用は抑えられますが、精神面や体力的な負担が大きく、挫折する可能性があります。
一方、業者に依頼する場合、費用負担はあるものの、短時間で手間なく片付けられます。
状況や予算に合わせて、自分に合った方法を検討しましょう。
費用負担だけでなく、時間や労力の負担感も含めての比較検討をおすすめします。
ためこみ症の片付け事例
ここでは、行政対応・業者の実例・家族による片付け体験を紹介します。
ためこみ症による片付けは、本人だけで取り組むのが難しいことも少なくありません。実際の現場では、行政による支援や専門業者の介入、家族と本人が協力して進めるケースなど、さまざまな事例があります。
東京都や横浜市での行政対応
ためこみ症が深刻化してゴミ屋敷化すると、行政が介入するケースがあります。
東京都では、「東京都生活環境保全条例」に基づき、近隣からの苦情や衛生上の問題が確認されると、所有者や居住者に対して改善を指導することになっています。
横浜市でも「ごみ屋敷対策条例」を制定し、地域包括支援センターや福祉部門が連携して、相談から支援、最終的には行政代執行に至るケースまで対応しています。
こうした制度は「強制的に処分する」のではなく、まずは住民や家族への支援を重視する点が特徴です。
出典:東京都環境局「生活環境の保全に関する条例」 / 横浜市資源循環局「ごみ屋敷対策」
業者による片付けの実例
粗大ゴミ回収隊では、ゴミ屋敷となった一軒家をわずか2時間で片付けた事例があります。
大量のゴミを2トントラック載せ放題プラン(59,800円)で回収し、短時間で生活再建可能な状態に戻しました。
“かなり大量のゴミが溜まっているように見えましたが、2トントラックに十分載せられる量でしたので、2トントラック載せ放題プランを適用させて頂き59800円で回収させて頂きました。作業は2時間ほどで完了いたしました。”
出典:—【粗大ゴミ回収隊 現場回収レポート】粗大ゴミ回収隊
家族と本人による片付け体験
実際に本人と家族が協力して片付けに取り組んだ体験談も報告されています。
長年ため込んだ衣類や紙類を手放すことは心理的に負担が大きく、本人が強い抵抗感を示す場面も多いですが、家族が寄り添いながら少しずつ仕分けを進めることで改善につながったケースです。
中には地域包括支援センターや福祉職員が立ち会い、第三者のサポートを得てようやく片付けが完了した事例もあります。
こうした取り組みは時間がかかるものの、本人の意欲を尊重することが再発防止においても重要とされています。
出典:NHK「ゴミ屋敷と向き合う」特集記事、全国紙の家庭記事(朝日新聞・読売新聞など)
片付け習慣を続ける工夫
ためこみ症の方に向けて、片付けを習慣化するためにできる工夫をいくつかご紹介します。
小さな取り組みで成功体験を積み重ね、片付けを習慣化していきましょう。
日常的に片付ける時間を作る
毎日5分~10分の短時間でも、片付けの時間を設定します。
例えば、以下のように時間や範囲を決めて継続すると片付けによる心地良さを体感でき、めんどうに思う気持ちが軽減されて意識向上にも効果的です。
- 朝食前の5分間でテーブルの上をすっきりさせる
- 帰宅したら玄関周りを5分間だけ整理整頓する
- 日曜日の朝は少し早起きして1時間だけ片付ける
小さな目標を設定して、目につきやすい場所から取り組み、達成感を得られるように工夫しましょう。
目標達成に応じた自分へのご褒美も有効です。片付けが生活の一部となれば、快適な環境を構築しやすくなります。
不要な物を増やさない工夫をする
ためこみ症の方にとっては、物の処分が非常に困難です。不用意に物を増やさないようにしましょう。
購入やもらい物など、家に物を増やす前に一呼吸おいて、以下の点を再確認すると意識も変わります。
- ないと困る物か
- 家にあるもので代用できないか
- 置き場所は確保できるか
- 捨てる際に困らないか
購入したりもらったりするのは簡単ですが、保管や管理、処分には手間だけでなく費用がかかることもあります。
安易に物を増やさないように、家に持ち込む前にしっかりと検討しましょう。不要なもらい物は断る勇気も必要です。
自分で難しい場合は業者に頼る
片付けの習慣化がどうしても難しい場合は、こまめに業者に依頼しましょう。
プロの手で迅速に生活環境を整え、快適空間で過ごす心地良さを体感してください。
費用をかけることで、少なからず意識も変わります。
サービス内容やプライバシーへの配慮など、業者によって対応が異なるため、事前に見積りを依頼して比較検討すると安心です。
ためこみ症への向き合い方
ここでは、家族や周囲の支援、生活習慣の見直し、サービスや専門機関の活用など、現実的に取り組める方法を紹介します。
ためこみ症は、本人の努力だけで改善するのが難しい場合が多く、周囲の理解や専門的な支援が欠かせません。
無理に片付けを迫ると対立や拒否感を強めることもあるため、協力的かつ段階的に進めることが大切です。
家族や周囲に協力してもらう
家族や友人が片付けをサポートすることで、本人が感じる負担や不安を和らげられます。
協力の際は「捨てなさい」と命令するのではなく、寄り添いながら一緒に仕分けを進める姿勢も重要。
小さな成功体験を積み重ねることで、片付けへの抵抗感が徐々に軽減されると報告されています。
出典:Mayo Clinic
生活習慣や住環境を整える
生活リズムや環境の改善は、ためこみ症の悪化を防ぐために役立ちます。
例えば「使ったら片付ける」「物を増やす前に処分する」といったシンプルなルールを生活に組み込むことです。
毎日の行動パターンを変えることが、物をため込まない習慣づけにつながります。
出典:Mayo Clinic
少しずつ物を手放す練習をする
ためこみ症の改善は一度に大量に片付けるのではなく、少しずつ「手放す練習」をすることが現実的です。
最初は不要なチラシや壊れた日用品など、感情的なつながりが薄い物から取り組むと続けやすくなります。
この段階的アプローチは、無理なく新しい習慣を身につけるのに役立ちます。
出典:Mayo Clinic
片付けを助けるサービスを活用する
片付けが自力では難しい場合、専門業者や地域の支援サービスを利用するのも有効です。
専門の片付け業者は分別から搬出、清掃まで一括対応してくれるため、短期間で環境を整えることができます。
また、消防機関など一部の公的機関が火災リスク低減の観点から支援に関与する例もあります。
自治体や地域の相談窓口を活用する
各自治体には、地域包括支援センターや保健福祉課など、片付けや生活支援の相談窓口が設けられています。
相談を通じて、清掃支援や生活支援サービス、場合によっては福祉制度の活用につながることもあります。
ひとりで抱え込まず、地域の仕組みを利用することが解決への一歩です。
出典:厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」
信頼できる情報源から学ぶ
ためこみ症に関する正確な知識を得ることは、改善の第一歩です。
インターネット上にはさまざまな情報がありますが、信頼性の高い公的機関や専門団体からの情報を参考にすることが重要です。
厚生労働省やNHS、Mayo Clinic、International OCD Foundationなどの資料は、エビデンスに基づく内容を提供しています。
出典:
必要な場合は専門機関や医療機関へ相談する
ためこみ症は専門的な治療や支援を必要とするケースが多いため、自己判断で抱え込むのは良い方法とはいえません。
症状が生活に大きな影響を与えていると感じた場合は、かかりつけ医や地域の精神保健福祉センターなどに相談するのがおすすめです。
医療機関での診断や治療は、再発防止にもつながります。
出典:NHS
まとめ|片付けは無理せず専門業者の活用も選択肢に
ためこみ症の方にとって、片付けや不用品処分は難易度の高い作業です。
短時間の片付けや掃除から習慣付けしていくと効果的とされています
不安な場合はまず専門業者への相談も選択肢です。その一つとして粗大ゴミ回収隊では無料見積りを受け付けています。
粗大ゴミ回収隊は、片付けプロがサポートしてくれるので、生活環境維持への意識向上にもつながるケースがあります。
快適空間を維持し、悪循環を抜け出す一歩を踏み出しましょう。
困ったときは無料相談がおすすめ
記事を読んでいて「結局どうしたらいいかわからない」「すぐになんとかしたい」「直接専門家に相談してみたい」という方も多いはず。そんなときは無料相談窓口を利用してみましょう!専門のオペレーターが対応いたします。
 に
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531
お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
に
 に
に
まずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

汚部屋・ゴミ屋敷の片付けでよくある質問
- 作業完了後にお支払いが可能
- 一括払い・分割払いから選べる柔軟な決済方法
- 信販会社との契約による安心・透明な仕組み
- 見積書にはクーリングオフの記載もあり、消費者保護が万全
- 部品やタイヤのサイズや数量によって料金が変動する場合がある
- オイルやバッテリーなどの液体を含むものは、回収可否が異なることがある
- 重量物の場合、搬出の際に追加費用が発生することがある
- 退去日が迫っており、早急に回収してほしい
- 搬出経路が狭く、自分では運び出せない
- 解体や分別が必要で作業が大変
- 他の不用品もまとめて回収してほしい
- お問い合わせ: 粗大ゴミ回収隊のサイトよりお問い合わせいただけます。
- 見積もり: 現地にて実際に回収する品物を確認し、見積もりを行います。
- 回収作業: 承認いただいた後に、安全かつ迅速に回収作業を進めます。
- 費用のお支払い: 作業完了後、ご指定いただいた方法でお支払いをお願いいたします。
Q 後払い決済対応は可能ですか?
はい、可能です。後払い決済をご希望の際は、以下の流れに従ってご対応させていただきます。
粗大ゴミ回収隊では、後払い・分割払いが可能です。
「今すぐ片付けたいけれど、手元に現金がない…」そんな場合でもご安心ください。
当社では、信販会社ライフティ株式会社の後払い決済サービス「WEぶんかつ」をご利用いただけます。
サービスの特徴
事前に「後払いを希望」とお伝えいただくだけで、手続きもスムーズに進められます。
回収サービスを安心してご利用いただけるよう、当社がしっかりサポートいたします。
Q ガレージに保管していた古タイヤや車部品の処分も対応していますか?
ガレージに保管していた古タイヤや車部品の処分も対応していますか?
はい、自家用車の不要部品や古タイヤ、工具類も回収可能です。
特にガレージに長年保管していた古タイヤやホイール、バッテリー、車のパーツなどは、処分方法に悩まれる方が多いですが、粗大ゴミ回収隊ではこれらの回収にも対応しています。内容によっては別途料金が発生する場合がございますので、以下のような点を事前にご確認いただくと安心です。
もし処分をご検討中の場合は、回収品の種類や量、保管状況などを詳しくお聞かせいただけますと、より正確なお見積もりが可能です。お手数ではございますが、ぜひ一度粗大ゴミ回収隊の公式サイトからお気軽にお問い合わせください。スムーズな回収のご案内をさせていただきます。
Q 引っ越しに合わせて壊れたベッドフレームだけ処分したいです
壊れたベッドフレームの回収について
はい、壊れたベッドフレームの回収も承っております。分解作業も含めてお任せいただけますので、重くて処分が難しい家具も安心してお任せください。
引っ越しに伴うベッドフレーム処分をご検討の方へ
引っ越しを機に、壊れたベッドフレームだけを処分したいというご相談も多くいただきます。粗大ゴミ回収隊では、以下のようなご事情にもしっかり対応しております。
ベッドフレームはサイズが大きく重量もあるため、処分する際は搬出の安全性や解体の手間が問題になることが多いですが、当社ではスタッフが分解から運び出しまで対応いたします。女性の一人暮らしやご高齢の方など、お一人では作業が難しい場合も安心です。
お見積もりやお問い合わせについて
粗大ゴミ回収隊では、お見積もりは無料で承っております。また、急なご依頼にも柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは、粗大ゴミ回収隊の公式サイトをご覧いただけますと、サービス内容や料金の目安をご確認いただけます。
引っ越しをスムーズに進めるためにも、壊れたベッドフレームの処分でお困りの際は、ぜひご相談くださいませ。
Q エアコンの配管ホースや金具だけの処分もできますか?
エアコン解体後の部品回収について
エアコン取り外し後に残った配管ホースや金具などの部品は、当社が丁寧に回収いたします。小さなパーツでも見逃すことなく、お客様のご要望に応じたサービスを提供しますので、ご安心ください。
よくある質問:配管ホースや金具だけの処分も可能ですか?
はい、可能です。不用品回収の専門業者として、エアコンの配管ホース、金具、ネジなどといった小さな部品まで、しっかり回収・処分いたします。こちらの作業は頻繁にご依頼いただく内容であり、経験豊富なスタッフが対応していますので、安心してお任せください。
不用品回収の流れ
さらに安心の不用品回収サービス
私たちは、お客様の疑問や不安を解消しながら、プロの視点で最適なサービスを提供しています。不用品回収に関する詳細や料金について知りたい方は、ぜひこちらをご覧ください。