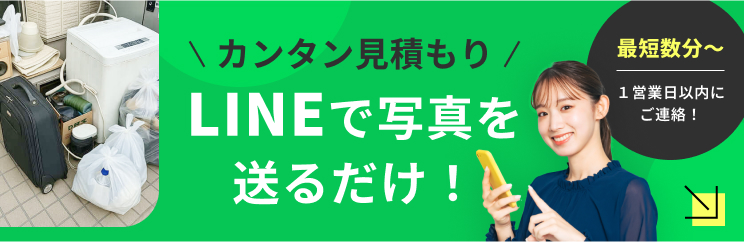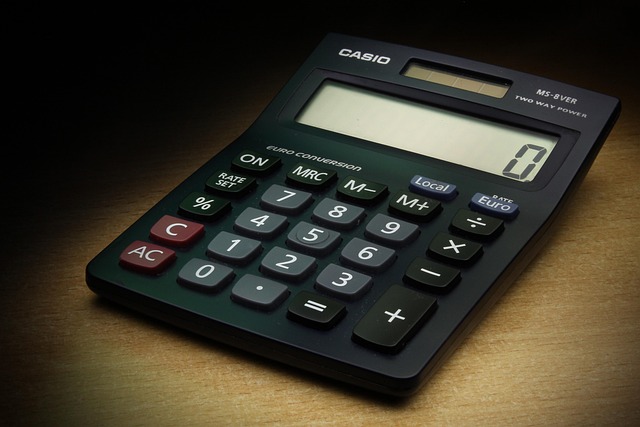空き家解体の費用を徹底解説!補助金や高くなるケース・安く抑えるコツ

空き家の解体にかかる費用を解説します。
費用相場は木造で1坪あたり3万~6万5,000円、30坪の戸建てなら90万~195万円です。
しかし、単に相場を知るだけでは不十分といえ、アスベスト除去や地中埋設物の処理などで追加費用が発生するケースもあります。
本記事を読めば、隠れたコストを含む解体費用の総額を予測できるほか、最大150万円の費用を削減できる補助金制度についても把握できるので、ぜひ参考にしてみてください。
目次詳細を見る詳細を閉じる
空き家解体費用の内訳

空き家の解体費用は複数の項目で構成されており、総額を正しく把握するためには、各費用の内容を理解する必要があります。
見積書には「解体工事一式」とまとめて記載されることもありますが、内訳を把握して適正価格かどうかを判断しましょう。
費用項目は主に5つに分類され、建物の規模や状態によって金額が変動します。
建物内の片付け・不用品処分費用
建物内に家具や家電、生活用品などが残っている場合は、解体工事前に片付けや不用品処分が必要です。必要な場合にのみ発生する費用なので、すでに空の状態であれば一切かかりません。
処分費用は間取りの広さに比例し、1Kで数万円程度、3LDK以上では数十万円かかることもあります。
専門業者に依頼する場合、作業スタッフの人数やトラックの台数だけでなく、不用品の種類により異なる場合もあるため、詳細な見積もりを取りましょう。
とくに、家電リサイクル法対象商品や大型家具が多い場合、追加費用が発生する可能性もあるため注意が必要です。費用を抑えたい方は、自分で処分する方法も検討してみてください。
建物の解体工事費用
建物を取り壊す作業にかかる費用は、重機や作業員による解体作業や基礎の撤去、整地作業などが含まれており、空き家の解体費用の中で最も大きな割合を占める項目です。
総費用の30~40%となり、建物の構造や延床面積で金額が大きく変動します。
費用の主な計算方法は、「坪単価×延床面積」ですが、木造や鉄骨造などの構造で坪単価が異なるため、注意しましょう。
同じ坪数でも2階建てより平屋のほうが基礎面積が大きくなり、解体費用が高くなる傾向があります。
また、都市部では人件費や廃棄物の処理費用が高くなるので、上記の目安を参考にしつつ高額な場合は理由を問い合わせましょう。
付帯工事と追加でかかる費用
建物以外にブロック塀やカーポートの解体、物置や庭木の撤去などの付帯工事が必要なケースもあります。付帯工事としてかかる内容と費用は、次のとおりです。
| 付帯工事項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 樹木や庭木の撤去 | 5,000~10万円/本 | 高さ、太さ、抜根の有無で変動 |
| ブロック塀の撤去 | 2,500~1万円/㎡ | 鉄筋の有無、高さ、厚みで変動 |
| 門扉の撤去 | 1万5,000~3万円/基 | サイズ、材質で変動 |
| カーポート撤去 | 2万~10万円/基 | 基礎の種類、サイズで変動 |
| 物置の撤去 | 1万~15万円/個 | サイズ、材質で変動 |
| 浄化槽の撤去 | 5万~10万円/基 | 清掃、消毒費用は別途3~5万円程度 |
| 養生・防音・防塵対策 | 1万~5万円 | 規模や現場条件で変動 |
ほかにも注意したい内容として、工事開始後に発見される地中埋設物や想定外のアスベスト含有材が挙げられます。
アスベストを例に挙げると、数十万~100万円の追加費用が請求されるケースもあるので、あらかじめ確認しましょう。追加工事が発生する条件と発生した場合の見積もりを出してもらうと、工事前に予算を確保しやすくなります。
廃材処分費用
空き家を解体したときに出る木材やコンクリートなどの廃材を処分するための費用も、解体工事費用に含まれます。廃材は種類ごとに分別して産業廃棄物処理施設で処理しなければなりません。
廃材処分費用の内訳は、次の4つの項目で構成されます。
- 分別作業費
- 運搬費
- 処理費
- 法定費用
上記の費用が含まれた形で、廃材の種類ごとに単価が異なります。下記の表で主な廃材処分費の目安を確認しましょう。
| 廃材の種類 | 処分費用の目安 |
|---|---|
| 混合廃棄物 | 1万8,000~2万5,000円/㎥ |
| 木くず | 1万2,000~1万6,000円/t |
| コンクリートガラ | 1,000~2,000円/t |
| 石膏ボード | 40~80円/kg |
| 金属くず | 1,000~5,000円/t(時価変動) |
| レンガ・瓦・ガラス | 10~30円/kg |
| 廃プラスチック | 4,000~1万3,000円/㎥ |
処分費用は、処理施設までの距離でも変動するので、立地による差も考えられます。近年は処理費用の高騰により、年々価格が上昇している点にも注意が必要です。
解体手続きにかかる費用
空き家の解体工事にはさまざまな手続きが伴うため、それぞれ費用が発生します。手続きの種類や費用目安は、次のとおりです。
| 手続き項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 建設リサイクル法の届出 | 0~1万円 | 解体業者による手続きが一般的で無料のケースが多い |
| 道路使用許可申請 | 2,000~3,000円 | 道路に足場や重機を置く場合に限り必要 |
| 建物滅失登記 (専門家依頼) |
4万~5万円 | 土地家屋調査士に依頼する場合 |
建設リサイクル法の届出は、延床面積80㎡以上の建物を解体する際に義務付けられています。施主に届出義務があるものの、解体業者が代行するのが一般的です。
建物滅失登記は解体後に必要な手続きで、1か月以内に申請しなければなりません。怠ると10万円以下の過料が科されるので、注意しましょう。
専門家に依頼すると4万~5万円ほどかかりますが、自分で手続きすれば1,000~3,000円で申請できます。
空き家の片付け・不用品処分費用の相場

空き家の片付けや不用品処分にかかる費用は、間取りの広さと残置物の量で大きく変動します。業者ごとに設定している料金も異なるので、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。
解体業者が提携する片付け業者を紹介されるケースもありますが、割高な場合が多いことから、それぞれの相場を把握したうえで検討しましょう。基本的には、自分で片付け業者を選ぶことがおすすめです。
間取り別片付け費用
片付け費用は間取りの広さに比例して高くなり、残置物の量でも変動します。間取り別の費用と作業の目安は次のとおりです。
| 間取り | 費用相場 | 作業人数 | 作業時間 |
|---|---|---|---|
| 1K・1R | 3万~8万円 | 1~2名 | 1~3時間 |
| 1DK | 5万~12万円 | 2~3名 | 2~4時間 |
| 1LDK | 7万~20万円 | 2~4名 | 2~6時間 |
| 2DK・2LDK | 9万~30万円 | 3~6名 | 3~8時間 |
| 3DK・3LDK | 15万~50万円 | 4~8名 | 5~12時間 |
| 4LDK以上 | 20万~60万円以上 | 4~10名 | 6~15時間以上 |
空き家を片付ける際に庭や物置にも残置物がある場合は、宅内と同時に片付けましょう。
屋外作業は別途料金が発生するので、自分で片付けられる範囲であれば、片付けておくと費用を抑えられます。
不用品回収処分費用
不用品回収の処分費用は、自治体の粗大ゴミ収集に自分で出すか、粗大ゴミ回収業者に依頼して搬出してもらうかで費用が大きく異なります。
ここでは、粗大ゴミ回収業者に依頼した場合の費用相場を紹介するので、依頼する際の参考にしてみてください。
| 品目 | 料金目安 |
|---|---|
| ベッド (シングル~ダブル) |
4,000~9,000円 |
| ソファ (1~3人用) |
3,000~8,000円 |
| タンス・食器棚 | 3,000~1万2,000円 |
| マットレス | 4,000~1万円 |
| 大型家具 | 3,000~1万円 |
上記のような品目別の料金だけでなく、不用品回収業者ではトラックに積み放題のプランが用意されている場合もあります。
軽トラックなら8,000~2万5,000円で依頼できるので、品目が多くなるようであれば見積もりを取って比較してみましょう。
下記の記事では、空き家の片付けにかかる費用の詳細に加え、安く抑えるコツを紹介しているので、あわせて読んでみてください。
空き家の解体費用相場|構造・坪数別の目安

空き家の解体費用の相場は、構造や坪数で次のとおりです。
| 構造 | 坪単価 | 30坪の解体費用目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 3万~6万5,000円 | 90万~195万円 |
| 鉄骨造 | 4万~8万5,000円 | 120万~255万円 |
| RC造 | 6万~15万円 | 180万~450万円 |
木造は解体が比較的容易にでき、廃材の処分費用も安いことから最も費用が低くなります。
対して、RC造(鉄筋コンクリート造)は、最も強固で重量もあり、廃材も混廃となることから解体費用が最も高くなるので、構造を把握したうえで予算を立てなければなりません。
ほかにも、立地条件や建物の劣化状況などが坪単価に影響します。下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ確認してみてください。
空き家の解体費用が高くなるケース

構造などの標準的な条件以外にも、空き家の解体費用はさまざまな要因で増加します。
立地条件や空き家の状態により、通常の1.5~2倍以上の費用がかかることも珍しくないので、事前に確認して増額に備えましょう。
空き家がゴミ屋敷だった場合|5万~80万円以上追加
解体する空き家がゴミ屋敷の場合は、先に片付けなければならないことから、5万~80万円以上の追加費用が予想されます。
| 状態 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 軽度 | 室内にゴミが散乱した状態 | 5万~15万円 |
| 中度 | 害虫が発生・足の踏み場がない | 10万~40万円 |
| 重度 | ゴミが膝上まで積み重なっている | 30万~80万円以上 |
ゴミの量や種類、悪臭の程度などの理由から高額になるので、ゴミ屋敷化してしまっているかどうかは事前に確認しましょう。
また、ゴミ屋敷の片付けは解体業者では対応できず、専門の業者を呼ばなければなりません。
片付け作業がすべて完了しないと着工できないため、解体工事を依頼する前に片付けておきましょう。
アスベスト除去が必要な場合|1万~8.5万円/㎡追加
2006年以前に建てられた建物には、アスベスト(石綿)が使用されている可能性があります。
アスベストが含まれている場合は、事前調査と専門業者による除去作業が法律で義務付けられており、解体工事前に除去しなければなりません。
アスベストは飛散性の高さごとにレベルが分けられており、除去費用が異なります。
| アスベストレベル | 主に使用されている場所 | 除去費用の目安 |
|---|---|---|
| レベル1(最も危険) | 天井、柱、梁の吹き付け材 | 1万5,000円~8.5万円/㎡ |
| レベル2(準飛散性) | 内壁、配管、柱の保温材 | 1万~6万円/㎡ |
| レベル3(低飛散性) | 屋根、外壁のスレート材 | 10万~60万円(30坪2階建て) |
レベル1のアスベストは非常に危険で、振動やちょっとした衝撃でも繊維が飛散するので、完全に密閉して作業しなければなりません。
アスベストの除去費用は、30坪の建物の総額で100万円を超える場合もあります。
レベル3のみであれば費用を抑えやすいものの、アスベスト除去が必要な場合は、高額な追加費用がかかることを把握しておきましょう。
道幅が狭い・重機が入らない立地の場合|1.5~2倍増し
空き家の前の道が狭くて大型の重機が入れない場合は、小型重機や手作業での解体となります。作業効率が低下して工期が長くなり、結果として人件費が増加します。
下記のような理由から、通常の1.5~2倍の費用がかかることも珍しくありません。
- 重機が使えず、すべて手作業となり時間がかかる
- 廃材を一輪車や手運びで搬出するため、小運搬費が増加する
- 狭小地では厳重な養生や特別な足場を設置する費用がかかる
30坪の木造住宅を例に挙げると、通常が90万~195万円の相場に対して135万~400万円になる可能性があります。
さらに付帯工事も含めると総額は500万円を超えることもあるので、費用の捻出や補助金制度の利用を検討しましょう。
地中埋設物の撤去が必要な場合|5万~100万円追加
解体工事を進める中で、地中から古い浄化槽や井戸、基礎杭や産業廃棄物が見つかることもあります。
撤去するには軽微な廃材で5万円~10万円程度、中規模の埋設物で10万円~50万円程度かかるため、空き家を解体する際は予算に余裕をもっておきましょう。
主な地中埋設物の撤去費用相場は、次のとおりです。
| 地中埋設物の種類 | 撤去費用の目安 | 主な発生場所 |
|---|---|---|
| 浄化槽 | 10万~50万円/基 | 下水未整備地域の旧住宅地 |
| 古井戸 | 5万~30万円/箇所 | 旧家屋・農地 |
| 地盤杭 | 5万円~/本 | 基礎が強固な構造の場所 |
| 地中埋設タンク | 3万~20万円/個 | 工場・ガソリンスタンド跡地 |
浄化槽や地下タンクなどは環境規制が関係するため、撤去作業は慎重におこなわなければなりません。そのため、費用が高くなるケースが多く、解体作業も一時的に中断してしまいます。
事前の地中調査で埋設物の有無が確認できれば予算を立てやすくなりますが、必ず見つけられるものではないので、工事中に発見された場合を考慮した予算組みが必要です。
建物内に家具や設備が残っている場合|3万円以上追加
建物内に家具や設備が残っている場合は残置物の撤去費用がかかるため、空き家の解体費用が高くなるケースに該当します。主な設備の撤去にかかる費用相場は、次のとおりです。
- システムキッチン:3万~8万円/式
- ユニットバス:5万~15万円/式
- 温水器・給湯器:1万~3万円/台
- 洗面化粧台:1万~2万5,000円/台
解体業者でも撤去できますが、事前に専門業者に依頼して取り外しておくことがおすすめです。また、照明器具は多くの解体業者で内装解体費に含まれますが、業者により別料金となる場合もあるため、見積もり時に確認してみてください。
設備が残っていると総額で数十万円の費用が追加されることもあるので、見積もりの時点で確認して専門業者と比較しましょう。
隣地との境界が近い場合|10~30万円追加
解体する空き家と隣家の距離が近い場合、近隣への対策として養生が厳重になったり重機を使わず解体したりします。そのため、養生にかかる費用や作業員の人件費が加算されるので、注意しましょう。
隣家との境界が近い場合の解体工事で発生する主な追加費用は、次のとおりです。
- 厳重な養生シート・防音パネルの設置:5万~15万円
- ガードマンの配置:1万~1万5,000円/日
- 手作業による解体作業:人件費が1.5倍程度に増加
上記に加え、境界杭の位置確認や測量が必要なケースでは、追加で20万~30万円かかる場合もあります。事前に隣家の所有者と境界立ち会いをおこない、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
空き家の解体費用を安くするコツ6選

空き家の解体にかかる費用は数百万円かかる大きな出費ですが、工夫すれば費用を安く抑えられます。自分でできることをおこない、業者の仕事量を減らせば数十万円の節約も可能です。
また、空き家の解体に関する補助金を活用できれば、最大150万円もの費用削減に期待できるので、ここで解説する解体費用を安くする6つのコツを確認しましょう。
補助金・助成金制度を活用する|最大150万円削減
各自治体では、放置されている空き家を減らすために、解体費用を補助する制度を設けています。解体費用の1/2が補助される場合や上限が150万円まで補助されるものなど、地域によりさまざまです。
国土交通省が自治体に対しておこなっている「空き家対策総合支援事業」の一環であり、各自治体に支援金が支給されています。そのため、個人が空き家を解体する際に補助金として受け取れる仕組みです。
補助金を受け取るためには、さまざまな条件があります。主な条件として、1年以上住んでいない空き家であることや旧耐震基準(1981年以前)の建物であることなどです。
なお、自治体によっては空き家バンクへの登録を条件とする場合もあるため、事前に確認しましょう。
3社以上の業者から相見積もりを取る|20~50万円削減
解体工事の見積もりを取る際、3社以上の業者から見積もりを取って比較すれば最も安く済ませられる業者に依頼できます。
複数社から見積もりを取り、比較して決めることを「相見積もり」と呼び、業者選びやサービスを比較するうえで重要な手順です。
相見積もりを取るために、次のポイントを押さえておきましょう。
- 同じ解体工事の条件で依頼する:正当に比較するため
- 現地調査に必ず立ち会う:認識のズレを防ぐため
- 相見積もりしていることを業者に伝える:安い金額を提示してもらいやすい
- 相見積もりする業者は多くても5社までにする:極端に多いと業者から敬遠される
解体工事の費用はある程度の相場はあるものの、業者により金額は大きく変動します。なかにはぼったくりのような悪徳業者の可能性もあるため、相見積もりを取って良心的な業者に依頼しましょう。
閑散期(6~9月、12~1月)に依頼する|10~15%削減
空き家の解体を依頼する際は、可能であれば閑散期を狙いましょう。建築業界の閑散期にあたる6月~9月、または12月~1月がおすすめです。業者のスケジューに余裕があり、値引き交渉の余地もあります。
繁忙期を避けて依頼すれば、総額の10~15%を削減できるでしょう。とくに6月~9月は引っ越しシーズンが終わり、依頼が落ち着く時期なので狙い目です。
梅雨や台風などが多いシーズンで解体工事がスムーズに進むか不安な方も多いですが、通常の雨なら解体工事は決行します。むしろ雨でホコリが舞いにくくなり、作業がスムーズになることもあるでしょう。
残置物や家財を事前に処分する|数万~数十万円削減
空き家内にある残置物や家財を事前に処分すれば、数万~数十万円の削減につながります。
残置物があるまま解体業者に見積もりを依頼すると、残置物の撤去も費用に含まれてしまうので、解体を検討した段階で処分しましょう。自力で処分するなら、次の方法がおすすめです。
- 自治体のゴミ収集に出す
- リサイクルショップに売る
- フリマサイトで譲渡または販売する
掃除や片付け、運搬の手間はかかりますが、費用を最小限に抑えられるので、時間が取れる方は少しずつ片付けてみましょう。
時間がない方や重い物を運ぶことが困難な方は、不用品回収業者への依頼がおすすめです。
解体業者に直接依頼する|仲介手数料を削減
空き家の解体工事はハウスメーカーや工務店で依頼するよりも、解体業者に直接依頼するほうが仲介手数料を削減できるので、安く済ませられます。
仲介手数料の相場は工事費の2~3割が一般的です。間に入った業者の利益分が乗っかる形となるので、200万円の解体工事でも40万~60万円が加算された形での見積もりとなるでしょう。
直接依頼すれば費用の内訳が明確になり、何にどれくらいの費用がかかっているのかを把握できます。
優良業者を探すことは難しいものの、実績のある業者を選んで相見積もりを取れば信頼できる業者を見つけられるので、慎重に探してみましょう。
庭木や雑草を事前に処理する|5~15万円削減
庭木や雑草の事前処理も、費用を削減できる方法の一つです。樹木の撤去は1本あたり3,000~2万円かかり、本数が多いと5万~15万円以上の費用になることもあります。
庭木の撤去費用は樹木の高さで変動し、高さ3m未満で3,000~1万5,000円、3~5mで1万~3万円、5m以上で2万~5万円以上が相場です。根を掘り起こす伐採作業は追加料金が発生します。
大きな樹木の場合は専門業者に依頼する必要がありますが、解体業者に依頼するよりも安く済むケースが多く、価値の高い樹木であれば買取も視野に入れて伐採可能です。
庭の整理は時間がかかる作業のため、解体工事の数ヶ月前から計画的に進めましょう。
空き家の解体費用を削減できる補助金制度

空き家の解体費用を削減できる補助金制度は、多くの自治体で実施されており、条件を満たせば数十万~200万円の支援を受けられます。
補助金制度を円滑に利用するためにも、申請条件や手順、注意点などをここで確認しましょう。
補助金の種類と支給額の目安
空き家の解体で利用できる補助金制度として、次の4つが挙げられます。
| 補助金の種類 | 支給額の目安 | 補助率 |
|---|---|---|
| 老朽危険家屋解体撤去補助金 | 30万~200万円 | 1/2~4/5 |
| 建て替え建設費補助金 | 50万~100万円 | 1/3~1/2 |
| アスベスト除去補助金 | 30万~200万円 | 1/2~2/3 |
| ブロック塀撤去補助金 | 10万~50万円 | 1/2~2/3 |
なかでも、老朽化家屋解体撤去補助金が空き家の解体で一般的に利用される補助金です。各自治体で補助金額は異なりますが、30万~200万円の範囲となるでしょう。
ただし、支給額がそのままもらえるわけではなく、補助率に応じて金額が決定します。
解体工事費用が200万円の場合に、最大100万円まで受け取れる補助金を利用しても、補助率が1/4であれば50万円までしか受け取れません。
支給額の上限のみで補助率を設けていない自治体もありますが、補助金制度を利用する際は、内容を詳細まで確認しましょう。
補助金の申請条件と対象の空き家
補助金を受けるためには、建物の条件と申請者の条件の両方を満たす必要があります。
片方の条件から外れると補助金の対象外となるので、事前に確認しておきましょう。対象となる空き家の主な条件は、次のとおりです。
- 1年以上誰も居住していない住宅(空き家)であること
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
- 木造または軽量鉄骨造の一戸建て住宅であること
- 屋根や外壁の崩れ、シロアリ被害、傾きなどがある老朽化した建物
- 自治体から「危険空き家」「特定空き家等」に指定されている建物
申請者の条件は、所有者または法定相続人であることが原則です。市区町村の住民税や固定資産税を滞納していないこと、反社会的勢力ではないことなども共通条件となります。
また、共有名義の場合は名義人全員の同意書が必要であるほか、法人所有の場合は対象外となるケースもあるため、詳細は自治体に確認しましょう。
補助金申請の手順と必要書類
補助金を受け取るには、必要書類を正しく揃えて適切な手順を踏む必要があります。申請から給付まで数ヶ月かかることもあるので、余裕をもったスケジュールで進めましょう。
申請から補助金受け取りまでの流れは、次のとおりです。
- 自治体の窓口に相談し、補助金制度の対象か確認する
- 解体業者から見積書をもらう
- 必要書類を揃えて自治体に申請する
- 自治体による審査・現地調査を受ける
- 交付決定通知を受け取る
- 解体工事を実施する
- 完了報告書と請求書を提出する
- 補助金が振り込まれる
必要書類は自治体により異なりますが、一般的には次のものがあります。
- 補助金交付申請書
- 建物の登記事項証明書または家屋評価証明書
- 解体業者の見積書の写し
- 建物の現況写真・案内図
- 固定資産税納税証明書
- 同意書
- 1年以上居住していないことの証明
相続人が申請する場合は、所有者が亡くなっていることを証する書類や申請者が相続権を有する証明書も必要になります。
補助金申請時の注意点
補助金を利用する際には、いくつか注意点があるので申請前に把握しておきましょう。
最も重要な注意点として、自治体ごとに予算が限られているため、なくなり次第終了する点です。そのため、空き家の解体を検討する段階で、補助金制度が利用できるかどうかも確認しましょう。
補助金申請時の主な注意点は、次のとおりです。
- 工事着手前に必ず申請する
- 審査に1か月程度かかる
- 予算がなくなり次第終了する
- 市内の指定業者の利用が必要な場合がある
- 解体後の土地利用に条件が設けられている場合がある
- 共有名義の場合は全員の同意書が必要
補助金が実際に振り込まれるのは工事完了後のため、一旦は解体費用を全額負担しなければなりません。資金計画を立てる際は、この点を考慮しておきましょう。
下記の記事では、空き家の解体で補助金を受け取る詳細の手順や、具体的な補助金の内容を一部の自治体を例に紹介しているので、あわせて読んでみてください。
費用をかけずに空き家問題を解決する方法

空き家の解体費用が捻出できない場合でも、空き家問題を解決する方法があります。
解体以外の選択肢を検討すれば、費用負担なく空き家を手放せたり収益化できたりするので、費用をかけたくない方におすすめです。
売却方法や活用方法を確認して、実践してみてください。
古家付き土地として売却する
空き家は解体せずに、建物が残ったまま古家付きの土地として売却可能です。買主が購入後に自分の判断で解体するか活用するかを決めるため、費用をかけずに空き家を手放せます。
古家付きの土地として売却する主なメリットは、次のとおりです。
- 解体費用がかからずコストを抑えられる
- 固定資産税の軽減措置が適用される
- 契約不適合責任を免責にしやすい
- 買主が住宅ローンを組みやすい
- 3,000万円特別控除の対象となりやすい
また、再建築不可物件の場合は、古家を取り壊すと二度と建物が建てられなくなるため、古家付き土地として売却する方法がおすすめです。
複数の不動産会社に査定を依頼し、古家付きと更地の両方の査定額を比較して検討しましょう。
不動産会社や買取サービスを活用する
不動産会社の買取サービスを利用すれば、空き家の状態にかかわらず現金化できます。仲介による売却と異なり、不動産会社が直接買い取るので、最短数日で売却可能です。
老朽化が進んだ空き家やゴミ屋敷状態の建物でも、専門の買い取り業者であれば対応可能なケースがあります。残置物がある状態でも売却できることから、片付けや清掃も必要ありません。
ただし、買取価格は市場価格よりも安くなるため、最大限の利益を求める方にはおすすめできません。また、最低でも3社以上の査定額を比較すると、より高値で売却できるでしょう。
空き家バンクを利用する
空き家バンクを利用すると、解体せずに空き家を再活用できるので、解体費用をかけずに問題を解決できます。
空き家バンクとは、自治体が運営する空き家のマッチングサービスで、空き家を売りたい人と買いたい人、貸したい人と借りたい人をつなぐ制度です。
無料で空き家を登録できるため、空き家の処分に困っている方におすすめのサービスといえるでしょう。
自治体の窓口から登録申し込みをおこない、審査を経て登録されると空き家バンクに情報が掲載されます。利用希望者から連絡が来たら直接やり取りして、交渉する流れです。
ただし、自治体が仲介業者のようなサービスをするわけではないことから、譲渡先は自分で探す必要があります。
リフォーム・賃貸として活用する
空き家をリフォームして賃貸物件として活用すれば、解体費用がかからないだけでなく、家賃収入につながります。初期投資は必要ですが、入居者が決まればかけた費用を徐々に回収可能です。
ファミリー層からシェアハウスまで、戸建ての空き家は活用先がいくつもあります。ただし、築年数が経過している物件では入居者が決まりにくいので、清潔感や機能性を重視した改修が必要です。
下記の記事では、空き家の解体費用がないときの対処法から空き家の活用方法まで解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
空き家解体工事の流れと期間

空き家の解体工事は、事前準備から完了まで複数の工程を経て進められます。スムーズに進められるよう、ここで確認しましょう。
事前に工事の流れや解体完了までの期間を把握しておけば、計画を立てやすくなります。
解体工事前|解体の準備と現地調査
解体工事をはじめる前に、信頼できる解体業者の選定が必要です。複数の業者から見積もりを取り、費用の内訳や工事期間、追加費用の有無を比較するため、3社以上見つけておきましょう。
業者を選定したら、現地調査を依頼して建物の状態や立地条件を確認してもらいます。
現地調査をしなければ正確な見積もりが出ないので、調査に立ち会って解体範囲や残す部分などを相談しながら決定してください。
また、補助金を利用する場合は、工事着手前に自治体に補助金交付申請書を提出し、自治体から交付決定通知を受け取ったあとに工事に着手してください。
交付決定前に工事に着手した場合、補助金は支給されません。申請から交付決定までには通常1か月程度かかるため、スケジュールに余裕を持たせておきましょう。
解体工事実施|工程と所要日数
解体工の実施は、安全性と効率性を考慮して段階的に進められます。所要日数は建物の構造や規模により異なりますが、木造30坪の住宅であれば10日程度が工期となるでしょう。
解体工事の主な工程と所要日数は、次のとおりです。
- 足場・養生の設置:1~2日
- 外構・屋根の撤去:1~3日
- 内装材・設備の撤去:2~4日
- 建物本体の解体:3~5日
- 基礎の撤去と整地:1~2日
- 清掃・重機搬出:1日
付帯工事や地中埋設物発見された場合は、さらに1週間程度の工期が必要になります。
また、建物本体の解体にかかる工期は、構造により大きく変わるので、詳細は必ず業者に確認しましょう。
解体工事完了|建物滅失登記の手続き
解体工事が完了したら、1か月位以内に建物滅失登記の申請をおこないましょう。登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があるので、忘れずに手続きしてください。
建物滅失登記とは、解体した建物が記録から削除されたことを公に証明する手続きで、法律で義務付けられています。
土地家屋調査士に依頼すれば、4万~5万円の費用で書類作成から申請まですべて代行してくれるので確実です。
自分で申請すれば数千円程度の費用で抑えられるものの、解体した空き家が所在する地域を管轄する法務局にて手続きしなければなりません。
オンラインでも申請できますが、法務局の方に相談しながら書類を作成したほうが間違いないでしょう。
空き家解体で失敗しない業者の選び方

業者を選びに失敗すると、ぼったくりや工事が粗い、整地不足などのトラブルにつながるリスクがあります。
トラブルを回避するためにも費用だけで判断せず、信頼できる業者を選ばなければなりません。許可証の確認から見積もりの内容など、チェックすべきポイントを解説するので、参考にしてください。
信頼できる業者の見極め方
信頼できる業者を選ぶためには、複数の観点から総合的に判断しなければなりません。まず確認すべきは、解体業の許可を得ているかどうかです。下記の資格を有しているかどうかを確認してみてください。
- 建設業許可または解体工事業登録
- 産業廃棄物収集運搬許可
登録されている業者なら、各都道府県や国土交通省のサイトで公開されているリストに掲載されているので、チェックしてから見積もりを依頼しましょう。
また、口コミや評判のリサーチも効果的です。実際に業者を利用した方の意見をしることで、作業品質や対応の良し悪しを把握できます。
見積書の正しい見方
見積書を確認する際は、内容の透明性を重視してください。内訳や備考欄まで細かく記載されているかどうかで、業者の良し悪しを判断しましょう。
総額が安く見えていても、必要な工事内容が記載されていない場合もあり、高額に感じた際は不要な付帯工事まで含まれている場合があります。
見積書でチェックすべきポイントは、次のとおりです。
- 内訳ごとに単価が表記されているか
- 「解体工事一式」で済まされていないか
- 廃棄物処理費が異常に安くないか
- 地中障害物の扱いが明記されているか
- アスベスト除去費用の扱いが記載されているか
- 室内残置物に関する記載があるか
複数の業者から相見積もりを取り、内訳が細かく記載されている業者を選びましょう。
地中障害物やアスベストに関しては、現地調査では発見できない場合もあるので、工事中に発見された際の対応や費用について記載がない場合は、確認が必要です。
契約時の注意点
解体業者と契約する際は、契約書の内容に注意が必要です。記載されていなければならない内容がない場合は、建設業法違反の可能性があります。
建設業法で定められている14項目の記載有無の確認は必須ですが、加えて確認すべき重要なポイントは、次のとおりです。
- 解体範囲が明確に記載されているか
- 見積もり金額から無断変更されていないか
- 支払い時期と方法が具体的に記載されているか
- 工期延長時の追加費用の扱いが記載されているか
- 契約不適合責任の所在が明確か(とくに地中埋設物やアスベスト発見時の責任分界点)
- 第三者への損害賠償責任が明記されているか
契約時にいずれか一つでも漏れている場合は、必ず確認してください。業者が記載しない旨を伝えてきた場合は、その場で契約せずに記載しなくてもよい内容なのかどうか精査しましょう。
業者選びに失敗しないためにも、業者の適切な選び方を把握しなければなりません。下記の記事でも解体業者の選び方について解説しているので、あわせて読んでみてください。
空き家の解体前に知っておきたい手続き

空き家を解体する際は、事前に知っておくべき手続きがあります。怠ると空き家を解体できなくなるほか、第三者とのトラブルにも発展しかねません。
それぞれの手続き内容を把握し、解体工事前に済ませましょう。
80㎡以上の建物の解体は建設リサイクル法の届出が必要
床面積80㎡以上の建築物を解体する場合は、建設リサイクル法に基づく届け出が義務付けられています。建設リサイクル法は、建設廃材の適正処理と再資源化の促進を目的として制定された法律です。
届出は着工の7日前までに所轄の自治体窓口に提出しなければなりません。仮に無届で解体工事をおこなうと、罰則規定が適用されるので注意しましょう。
また、届出の際は、届出書以外に分別解体計画や工程表、案内図や解体前の現況写真などの書類が必要です。
基本的に解体業者が代理で届け出てくれますが、発注者の義務となることから届出を済ませたかどうかを確認しましょう。
電気・ガスの停止は工事の2週間前までに連絡
解体工事がはじまる前に、電気やガスなどのライフラインの停止手続きが必要です。工事中に感電やガス漏れの事故を防ぐためにも、自分が各供給会社に連絡して停止しなければなりません。
ただし、水道については解体業者が水を使用するため、工事完了までは停止手続きをおこなわないでください。反対に、空き家で水道を通していない場合は、開始手続きをおこないましょう。
また、電気やガスは停止のみではなく、引き込み線やガス管の撤去作業が伴うこともあり、立ち会いが求められます。日程調整を含めてすべて2週間前には完了できるようスケジュールを調整してください。
近隣への挨拶や説明
空き家を解体する際は、近隣住民への事前周知が必要です。解体工事の騒音や振動などに対して苦情が寄せられることもあるため、トラブルを防ぐためにも必ず周知しましょう。
多くの自治体では事前周知要網を制定し、標識の設置と近隣への説明を義務付けています。説明のタイミングと範囲は、次のとおりです。
- 説明時期:工事着手の7~15日前まで(自治体に要確認)
- 説明範囲:敷地境界線から建物の高さに等しい水平距離の範囲内(最低でも10m)
- 説明方法:説明会の開催、戸別訪問、説明資料の配布
説明すべき内容は、工期や作業時間、解体方法などに加え騒音や振動、粉塵に対する防止策などが挙げられます。
多くの解体業者は近隣挨拶に同行してくれるので、内容がわからないときは業者に相談しましょう。
解体前のお祓い
解体工事をおこなう前にお祓いをしたい方は、「解体清祓」と呼ばれる儀式をおこないましょう。
解体清祓は、家屋の守り神に対してこれまで見守ってくれた感謝と、これからおこなう工事が無事に終わるよう祈願する儀式です。
長く暮らしていて家自体に思い入れがある場合や、気持ちの整理をつけたい場合に執りおこないます。
費用相場は合計で5万~6万円です。神社により神主の出張費が別途かかる場合もあるので、依頼時に確認しましょう。
解体の際のお祓いにはいくつか種類があり、解体清祓以外のお祓いについても確認したい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
また、家の解体手続きの詳細については、下記の記事にて解説しているので、細かく知りたい方はあわせて読んでみてください。
空き家解体後の税負担増加への対策
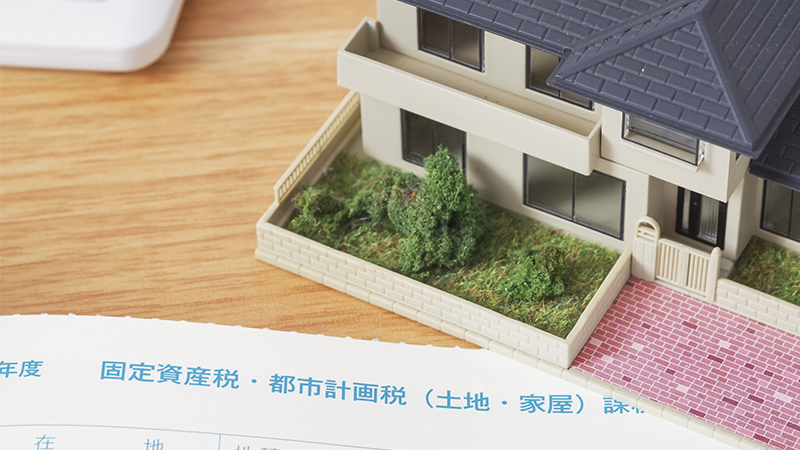
空き家を解体して更地にすると住宅用地特例と呼ばれる減税制度が適用されなくなるため、土地の固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍に跳ね上がります。
そのため、空き家解体後の税負担の増加への対策が必要です。ここで解説する対策を把握したうえで解体に臨めば、税負担を最小限に抑えられます。
解体タイミングを年始に調整する
固定資産税の課税判断は毎年1月1日におこなわれるので、解体のタイミングを年始に調整すると税負担を軽減できます。
1月1日時点で建物が存在していれば住宅用地特例が適用され、翌年度の固定資産税を軽減可能です。反対に12月31日までに解体が完了すると、翌年1月1日の時点で更地として課税されるため、注意しましょう。
具体的な方法としては年末に向けて解体工事の準備を進め、年明けすぐに着工できるよう調整してみてください。また、見積もりや現地調査の際に業者に伝えておくと、スケジュールを考慮してくれるでしょう。
更地にせず古家付き土地として売却する
税負担の増加を避けるための方法には、更地にせず古家付き土地として売却する方法も挙げられます。
建物が残っている状態で売却すれば、住宅地特例が適用されたまま買主に引き渡せるため、売却までの固定資産税の負担が最小限に抑えられるでしょう。
ただし、買い手が見つからなければ空き家が放置されたままとなるので、再び解体を視野に入れなければなりません。空き家バンクや不動産売買などを活用して、早めに売却できるよう努めましょう。
相続・売却時の特例を活用する
相続した空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を活用すれば、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
譲渡益が生じる場合に活用すれば、所得税や住民税の負担を大幅に軽減できるでしょう。特例を受けるための主な要件は、次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
- 相続開始から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 区分所有建物ではないこと
- 相続開始の直前に被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
- 相続してから売却するまでに事業用・貸付用・居住用として使用していないこと
また、特別控除を受けるためには確定申告が必要で、「被相続人居住用家屋等確認書」を提出しなければなりません。
下記の記事では相続した際や相続を放棄した際の空き家の解体費用を払う方が誰になるのか、具体的に解説しているので、あわせて読んでみてください。
空き家解体の業者選びに迷ったときは
空き家解体の業者選びに迷ったときは、事前相談から建物の解体まで一括依頼できる「粗大ゴミ回収隊」を検討してみましょう。
空き家の解体工事はもとより、残置物処分や遺品整理にも対応できるので、まとめて手続き可能です。また、補助金や税金などの制度にも対応していることから、費用負担を最小限に抑えやすくなります。
不用品回収と解体工事を一括依頼すれば、総額から15%オフになるキャンペーンも実施中なので、ぜひ相談してみてください。
>>>粗大ゴミ回収隊への無料見積もりはこちら!
困ったときは無料相談がおすすめ
記事を読んでいて「結局どうしたらいいかわからない」「すぐになんとかしたい」「直接専門家に相談してみたい」という方も多いはず。そんなときは無料相談窓口を利用してみましょう!専門のオペレーターが対応いたします。
 に
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531
お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
に
 に
に
まずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

空き家の解体費用でよくある質問
-
Q 相続した空き家を解体するか売却するか迷った場合、どのように判断すればよいですか?
A.空き家の老朽化や修繕費、維持費を考えると、活用予定がない場合は解体や売却を検討する価値があります。
土地として売るか、古家付きで売るかで売却額が変わるため、両方の査定を比較すると判断しやすくなります。
地域の需要によっては、更地より古家付きの方が売れやすいケースもあります。
固定資産税や管理負担も含めて、総合的に比較することが大切です。 -
Q 解体費用を少しでも抑えるためにできる工夫はありますか?
A.複数業者から相見積もりを取るだけでも、数十万円の差が出る場合があります。
内装材や再資源化できるものを分別しておくと、処分費が抑えられる可能性もあります。
補助金制度を利用できれば、自己負担額を大きく減らせます。
時期によって料金が変動することもあるため、余裕があれば閑散期の依頼も検討してください。 -
Q 解体後の土地を放置すると、デメリットがありますか?
A.雑草や不法投棄など管理リスクが高まり、近隣トラブルにつながる可能性があります。
状態が悪化すると、整地や清掃の費用が発生することもあります。
活用しないまま固定資産税を払い続けるのは負担となりやすいです。
早めに売却や活用計画を立てておくと無駄なコストを防げます。 -
Q 家の解体前に、持ち主が必ずやっておくべき手続きはありますか?
A.ライフライン(電気・ガス・水道)の停止手続きは事前に済ませておく必要があります。
ご近所への挨拶や工事期間を知らせておくと、トラブル防止に役立ちます。
残置物の撤去を前もって進めておくと、追加料金の発生を防ぎやすくなります。
解体に必要な許可や届出についても、業者と相談しながら確認しておくと安心です。 -
Q 解体工事中にトラブルが発生した場合、誰に責任があるのですか?
A.通常は解体業者が施工に関する責任を負いますが、契約内容によって範囲が異なります。
近隣トラブルや破損事故が起きた際の対応方法が契約書に明記されているか確認が必要です。
保険に加入している業者であれば、万が一の損害にも対応できて安心です。
契約前に「補償」「保険」「近隣対応」の有無を必ずチェックしてください。