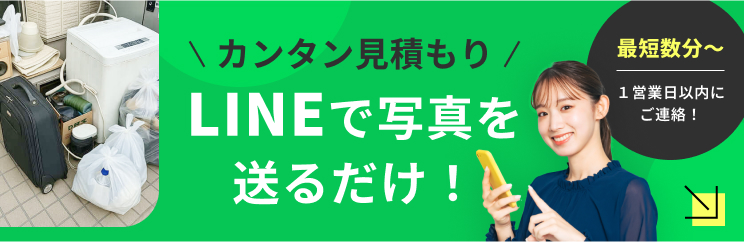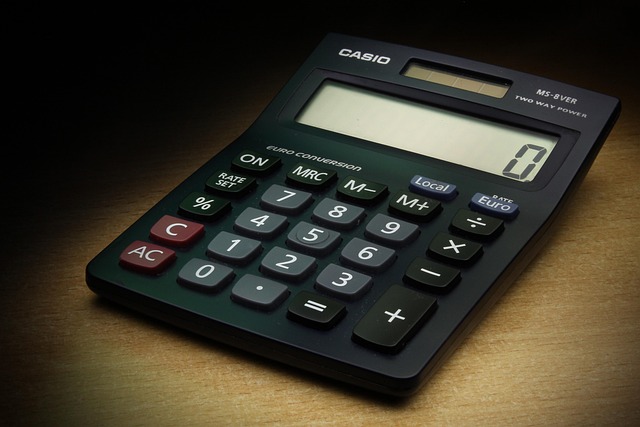
空き家の解体費用がないときの対処法と安く抑えるコツを一挙解説

空き家を解体するにはまとまった費用がかかるため、資金を用意できずに悩む方が増えています。
しかし、空き家を放置すると倒壊や放火など、大きなトラブルに発展する可能性があり、早めの対処が必要です。
本記事では、空き家の解体費用がないときの対処法や費用を安く抑えるコツを紹介します。
空き家問題をスムーズに解消するために役立ててください。
目次詳細を見る詳細を閉じる
空き家の解体費用がないときの7つの対処法

空き家の解体費用を用意するのが難しい場合は、補助金制度の利用や売却も検討してみましょう。金銭的な負担を軽減できる可能性があります。
空き家の解体費用を誰が負担すべきかについては、以下の記事をご覧ください。
補助金制度を利用する
国や自治体が提供する空き家の解体にかかる補助金制度を利用すれば、費用負担を減らせます。
空き家がある地域の自治体が補助金制度を提供している場合、条件が合えば数十万円の支給が受けられる可能性があります。
補助金制度の対象となるのは、主に倒壊の恐れがあるような空き家です。
例えば、東京都では「東京都空き家家財整理・解体促進事業」として、10万円を限度として解体費用の半額を補助する制度があります。
ただし、制度のない自治体もあります。
空き家がある自治体の窓口で、補助金の有無や条件などを確認してみましょう。
家の解体の補助金については、以下の記事で詳しく解説しています。
売却契約後に解体する
空き家を残した状態で「更地渡し」として売却する方法があります。
「更地渡し」とは、空き家などがある状態で土地の売買契約を締結したあとに、売り主負担で建物を解体し更地にして買い主に引き渡す不動産取引で、自己資金がなくても、土地の売却益で解体費用をまかなえます。
ただし、契約後の解体となることから予期せぬトラブルが発生するリスクがあるため、契約時には仲介業者を介して双方の認識にずれがないように進めることが重要です。
不動産会社などに売却する
数は少ないものの、空き家のある土地を買い取る不動産会社や土地買取業者があります。
解体費用がない場合はその土地のある地域で、買い取りに対応する業者を探して相談してみるといいでしょう。
不動産業者などに直接売却する場合は、解体費用の負担もなく短期間で売却できる点が魅力ですが、一般的な仲介による売買に比べて価格が低くなる傾向にあります。
空き家解体ローンを利用する
「空き家解体ローン」とは、その名のとおり空き家を解体するための専用ローンです。
数十万円から500万円ほどの融資金額を年率2.0~4.0%ほどの低金利で借り入れできるローンで、返済期間も最長10~15年と優遇されています。
銀行や信用金庫、JAなどで取り扱いがあります。
補助金の利用や売却がすぐに難しい場合でも、ローンと併用すれば資金確保が可能です。
古民家付き土地として売却する
古民家としての価値や活用の可能性がある場合は、建物をあえて残して売却する方法も検討しましょう。
近年では古民家をリノベーションしたカフェや民泊が増えており、需要が見込めるエリアでは解体せずとも売却できる可能性があります。
建物に文化的な価値がある場合は、保存目的の団体が購入するケースもあります。
賃貸物件として運用する
賃貸の需要が見込める地域であれば、修繕やリフォームをして賃貸物件として運用する方法もあります。
空き家の状況や周辺の需要などを含め、賃貸に出せるか不動産業者に相談してみましょう。
入居者が見つかれば、毎月家賃収入を得られます。一時的に賃貸に出し、その賃料を後の解体費用に充てることも可能です。
ただし、賃貸するために修繕費用がかかる場合は、賃貸需要や賃料相場をしっかりと調査して収支シミュレーションしたうえでの検討が必要です。
空き家バンクなどに登録する
「空き家バンク」に登録すると、空き家がある状態でも買い手が見つかる可能性があります。
空き家バンクとは、自治体のホームページなどで空き家物件情報を提供する仕組みのことです。
空き家を売却・賃貸したい人と、購入・賃貸したい人とをマッチングさせ、地域への定住を促進するための制度です。
地元の空き家情報を募集し、移住を検討している方に向けて物件情報を提供しています。
自治体が窓口となっていますが、交渉や契約は当事者間でのやりとりになります。
後のトラブルを避けるために、仲介手数料を支払って不動産会社に仲介を依頼することも可能です。
空き家がある状態で物件を登録し、買い手がつけば解体費用を負担せずに済みます。
空き家の解体費用を安く抑えるコツ

解体費用は、同じような建物でも依頼先や時期などによって数十万円単位の差が出ることがあります。
解体費用を少しでも安く抑えるために、以下の4つのコツを紹介します。
不用品処分から解体までを1社に依頼する
不用品処分と解体の両方に対応している業者では、まとめての依頼で料金が割引されるケースがあります。
不用品の搬出・処分から解体まで、作業工程をまとめて効率化できるため、総費用の交渉もしやすくなります。
「粗大ゴミ回収隊」では、今なら不用品処分と解体の同時申し込みで総額から15%OFFになりお得です。
依頼の際は事前に見積もりを依頼し、作業範囲がどこまで含まれるのか、追加費用が発生しないか、内容をしっかりと確認しましょう。
複数業者に相見積もりを依頼する
2~3社に相見積もりを依頼すると、解体業者の価格相場やサービス内容、担当者の対応なども比較しながら検討できるのはもちろん、料金交渉もしやすくなります。
料金だけでなく、細かな作業内容やサービス内容もチェックしましょう。
見積書に「解体工事一式」などとして内訳の記載がない場合は、どこまでが料金に含まれているか不明で、不当な追加費用が発生するリスクがあるため内容の確認が必要です。
見積もりが安すぎる場合も、追加費用の発生や不法投棄などのリスクが考えられるため、妥当性があるか確認して検討しましょう。
解体工事で損をしない見積もり方法の解説記事もご覧ください。
閑散期に依頼する
年度末などの繁忙期を避け、業者の稼働率が下がる時期に解体工事を依頼すると、比較的単価が低くなり費用を抑えられる傾向にあります。
繁忙期は需要があるうえ、人手不足で人件費も高額になりがちですが、閑散期は需要が減り供給過多となるためです。
工期に余裕をもって計画すると、柔軟に割引交渉や日程調整が可能となるため、早めの検討をおすすめします。
付帯工事などを自力で処理する
付帯工事のうち、自力でできるものがあれば、その分の費用を節約できます。
例えば植栽の伐採や抜根、物置の撤去など、自分でできそうな部分を検討してみるといいでしょう。
ただし、重量物や重機が必要となるなど危険度の高い工事は無理に手をかけず、専門業者に任せることをおすすめします。
空き家の解体費用相場
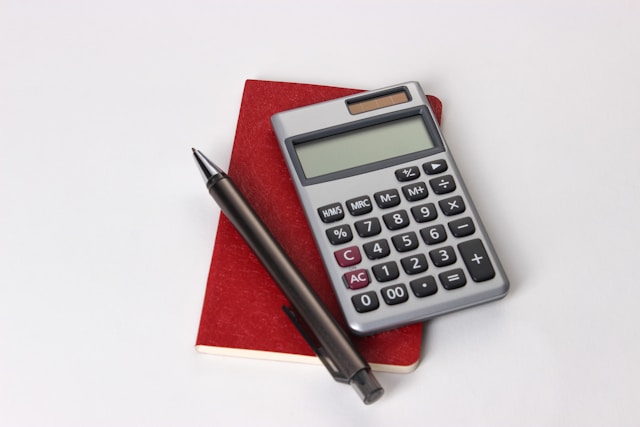
空き家の解体費用相場は以下のとおりですが、建物の構造や規模、状態、立地条件、残置物の量などにより大きく変動します。
| 建物構造の種類 | 解体費用の相場(坪単価) |
|---|---|
| 木造 | 30,000~50,000円 |
| 鉄骨造 | 40,000~60,000円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 60,000~80,000円 |
一般的な木造住宅に比べると、鉄骨造や鉄筋コンクリート造住宅は作業工程が多くなるため、費用は高額になります。
費用相場を踏まえて相見積もりで比較検討すれば、地域の相場感も把握しやすくなるでしょう。
空き家の解体費用について詳しくは、以下の記事で解説しています。
→「空き家 解体」親記事へリンク
空き家の放置によって発生するリスク

空き家を放置すると、以下のようなリスクが高まるため注意が必要です。
税負担が増える
空家の増加が深刻な社会問題になっていることから政府は対策を強化し、令和5年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。
法改正により「特定空き家」に加え、「管理不全空き家」も、固定資産税の優遇措置「住宅用地の特例」の適用外となりました。
住宅が建っている土地については、住宅用地の特例により、以下のとおり固定資産税が優遇されます。
| 住宅用地 | 課税評価額 |
|---|---|
| 小規模住宅用地 (200㎡まで) |
・固定資産税:1/6 ・都市計画税:1/3 |
| 一般住宅用地 (200㎡を超えた部分) |
・固定資産税:1/3 ・都市計画税:2/3 |
しかし、「特定空き家」「管理不全空き家」に認定されると、住宅用地の特例の適用外となり、土地の固定資産税が最大で約6倍になります。
税負担が重くなれば、解体費用の予算もさらに削られるでしょう。
早めに解体を済ませ、土地活用を検討したほうが無駄なコストを抑えられます。
近隣トラブルに発展する
空き家は老朽化が進みやすく、害虫や害獣の発生、雑草や庭木の越境、家屋の倒壊、不法投棄、不審者の出入り、放火などが懸念されます。
例えば、空き家の外壁が落下して通行人が負傷した場合など、損害賠償を請求されるリスクもあるため注意が必要です。
近隣からの苦情により、行政指導など自治体が介入する事態に発展するケースもあります。
不法投棄された場合は、投棄した人を特定できない限り、原則として空き家の所有者が処分費用を負担しなければなりません。
以上のように、近隣トラブルに発展するレベルになると、解体だけでは済まなくなる可能性があります。
早めの対処で、リスクを最小限に抑えましょう。
50万円以下の過料に処せられる
「特定空家等に対する措置」の規定による市町村長の命令に違反すると、50万円以下の過料に処せられるため、指導や勧告には従いましょう。
市町村長は特定空き家の所有者に対し、除却や修繕、立木竹の伐採など、地域の生活環境を保全するために必要な措置をとるように、助言または指導ができます。
それでも改善がなされない場合は、猶予期限を示して勧告、勧告にも応じなければ命令となり、違反すれば過料に処せられるわけです。
自治体が介入するような問題に発展する前に、できるだけ早い段階で適切に対処しておくことをおすすめします。
空き家の解体費用が安い業者を比較して決めよう

空き家の解体費用がない場合は、補助金の利用や売却後の解体、空き家解体ローンなどを検討しましょう。
解体費用を安く抑えるには、不用品処分と解体を一括で依頼できる「粗大ゴミ回収隊」をご検討ください。
今なら、不用品回収と解体の同時申し込みで、総額から15%値引きとなるお得なキャンペーンを実施しています。
お気軽にご相談ください。
困ったときは無料相談がおすすめ
記事を読んでいて「結局どうしたらいいかわからない」「すぐになんとかしたい」「直接専門家に相談してみたい」という方も多いはず。そんなときは無料相談窓口を利用してみましょう!専門のオペレーターが対応いたします。
 に
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】
 0120-84-7531
0120-84-7531
お支払い方法
現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い
(分割払い可)


 に
に
 に
に
まずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法
現金

銀行振込

後払い
(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

空き家解体費用についてよくある質問
-
Q 補助金制度は、どんな空き家でも利用できますか?
A.補助金は「倒壊の恐れがある」「周辺環境に悪影響が生じている」など、条件を満たす空き家が対象になることが多いです。
自治体ごとに補助金の有無や支給額、対象基準が異なる点に注意が必要です。
事前審査や書類提出が求められる場合があるため、早めに確認するとスムーズです。
まずは空き家所在地の自治体窓口へ相談してみると良いでしょう。 -
Q 「更地渡し」で売却する場合、どんなリスクがありますか?
A.売却契約後に解体を行うため、解体費用が予定より高くなると負担が増える可能性があります。
買主との認識共有が不十分だと、解体範囲や時期を巡るトラブルが起きやすくなります。
不動産会社を介して契約内容を明確にしておくと、トラブル防止につながります。
契約前に解体費用の見積もりを複数取っておくと安心です。 -
Q 古民家として売却する場合、どういった物件なら需要がありますか?
A.観光地や移住人気の高い地域では、古民家カフェや宿泊施設への活用需要があります。
建物の状態や築年数よりも、風情や構造が評価されるケースも見られます。
文化的価値がある場合は、保存目的で購入される可能性もあります。
まずは地域の不動産会社へ相談して、需要が見込めるか確認してみてください。 -
Q 空き家解体ローンを利用するのは、どんな人に向いていますか?
A.補助金や売却がすぐに見込めない場合でも、ローンを利用すれば解体資金を確保できます。
年2.0~4.0%ほどの低金利で借りられるケースが多く、毎月の返済負担を抑えやすいです。
解体後の土地活用で収益化を予定している人にも向いています。
ただし返済計画を立てたうえで利用することが大切です。 -
Q 空き家を放置すると、具体的にどんな費用負担が増える可能性がありますか?
A.「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が外れ、税負担が最大約6倍に増えます。
放置により害獣被害や破損が発生すると、修繕費や損害賠償が発生する場合もあります。
状況が悪化すると行政指導や命令につながり、最終的には過料の可能性もあります。
早期に売却や解体を検討するほうが、長期的なコストを抑えられます。